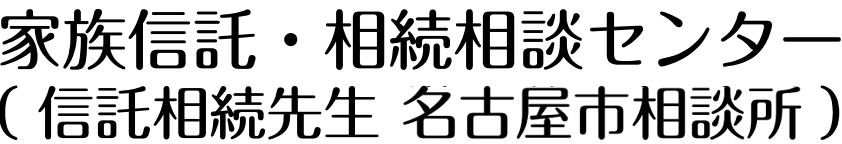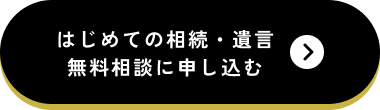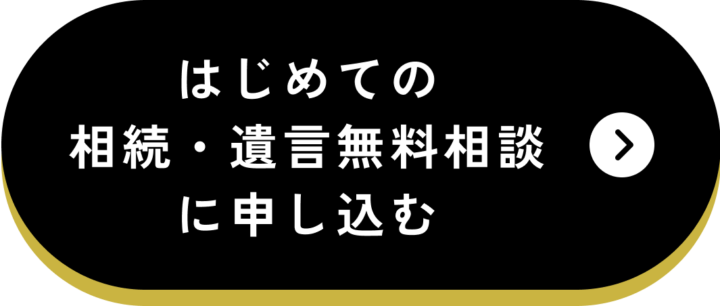相続税申告は自分でできる?手続きの流れと専門家に依頼するメリット
- 公開日:
- 更新日:
親の相続が発生したとき、「相続税申告は自分でできるのだろうか?それとも専門家に任せるべきか?」と悩む方も多いでしょう。特に高齢の親を持つ50代の子世代にとって、相続税申告を自力で進めるべきか、あるいは税理士など専門家に任せるべきかは大きな判断ポイントです。本記事では、相続税申告を自分で行う場合の基本的な手続きの流れから、自力で申告する際の注意点、そして税理士など専門家に依頼するメリットや依頼時の費用相場・専門家の選び方まで、中立的な立場でわかりやすく解説します。相続税申告を自分で行うか専門家に任せるか迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
自分で相続税申告を行う際の基本手続き
相続税の申告手続きは大きく分けて以下の流れで進めます。相続発生から申告・納税までは、被相続人の死亡から10か月以内という期限があるため、計画的に手続きを進めましょう。
財産目録の作成(資産・負債の洗い出し)
まずは被相続人が残した財産の全体像を把握することが出発点です。プラスの財産とマイナスの財産をすべて洗い出し、「財産目録(遺産目録)」を作成します。プラスの財産には現金・預貯金、株式などの有価証券、不動産(土地・建物)、自動車、美術品・骨董品など、そして死亡保険金や死亡退職金といった相続で受け取る財産も含まれます。一方、マイナスの財産としては被相続人に借入金などの債務があればその残高、未払いの税金や医療費、葬儀費用などもリストアップします。これらを漏れなくリスト化することで、相続財産の全体額を把握でき、後の相続税額の試算に役立ちます。
※なお、生前に被相続人から相続人へ3年以内に贈与された財産がある場合や、生前贈与で相続時精算課税を適用して受け取った財産がある場合は、それらも相続財産に加算される点に注意が必要です。また、被相続人が残した遺言書の有無もこのタイミングで確認しておきましょう。
各資産の評価額算出と相続税額の試算
財産目録ができたら、次に各資産の評価額(相続税評価額)を算出します。現預金は残高がそのまま評価額になりますが、不動産などは相続税独自の評価方法(例えば路線価や固定資産税評価額にもとづく計算)を使って評価します。株式や投資信託なども所定の方法で評価し、すべてのプラスの財産評価額の合計からマイナスの財産を差し引いた正味の遺産額を算出しましょう。正味の遺産額が算出できたら、相続税の基礎控除額と比較します。基礎控除額とは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される非課税枠のことで、遺産額がこの枠内で収まる場合には相続税はかかりません。遺産総額が基礎控除を超える場合に相続税の申告・納税が必要ですので、自分で申告する場合でもまず基礎控除額を算出してみましょう。例えば法定相続人が配偶者と子1人の合計2人なら基礎控除額は4,200万円になります。この額を超える遺産がある場合には相続税申告が必要です。
課税対象となる場合には、続いて相続税額の試算を行います。相続税の税率は累進課税(課税額が大きいほど税率も高くなる方式)で10%から最大55%まで段階的に定められていますが、実際の計算は法定相続分に応じて各人の税額を出す方式でやや複雑です。自分で正確に計算するのは難しいため、国税庁のホームページにある「相続税の申告書作成コーナー」などのシミュレーションを利用すると良いでしょう。
相続税申告書の作成と税務署への提出方法
相続税申告書は国税庁から書式を入手し、自分で記入して作成します。被相続人の氏名や住所、相続人の氏名、各人が取得した財産の種類と金額、適用する控除や特例の有無などを記載します。申告書は第一表から第十五表まであり、不動産や有価証券の明細、債務控除額の明細など様々な付表がありますが、該当するものを選んで記入します。作成した申告書と必要添付書類一式は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に提出します。提出は税務署窓口への持参か郵送で行え、またマイナンバーカードなどを利用した電子申告(e-Tax)による提出も可能です。なお、相続税の納税も申告期限と同じく死亡から10か月以内に完了させなければなりません。金融機関の窓口で納付するほか、インターネットバンキングやクレジットカード納付なども利用できます。申告書の提出と納税が揃って初めて相続税の手続き完了となる点に注意しましょう。
以上がご自身で相続税申告を行う場合の基本的な手続きです。慣れない作業も多いため、早めに準備に着手することが肝心です。特に戸籍の収集や不動産評価には時間がかかるため、余裕を持って計画しましょう。分からない点があれば税務署の電話相談窓口(タックスアンサー)や相続専門の税理士に相談することも検討してください。
自分で申告する場合の注意点
自分で相続税申告を行う際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
複雑な財産評価や特例適用漏れ
まず、複雑な財産評価や特例適用漏れによる申告誤りのリスクです。相続税の土地評価は路線価図を使った複雑な計算が必要ですし、小規模宅地等の特例や配偶者控除など、適用できる控除・特例を見落とすと本来より多く税金を納めてしまう可能性があります。逆に誤った適用で税額を少なく計算してしまうと、後日の税務調査で指摘され延滞税や加算税が課される恐れもあります。専門知識が要求される不動産評価や特例の判断に自信がない場合、無理せず税理士に相談し、チェック・助言を受ける方が安心でしょう。
必要書類の収集と書類不備による手続き遅延
次に、必要書類の収集と書類不備による手続き遅延の注意です。前述したように相続税申告には多くの添付書類が求められ、戸籍謄本や住民票、残高証明書や評価証明書など準備すべき資料が多岐にわたります。これらの収集には時間がかかりますし、1つでも漏れがあると税務署が申告書を受理せず差し戻されることもあります。提出期限ギリギリになって「必要な書類が足りない!」と慌てることのないよう、チェックリストを活用して早めに書類集めを進めましょう。なお、法務局の法定相続情報証明制度を利用して法定相続情報一覧図を作成しておけば、戸籍の束の代わりにその一覧図を提出書類として使えます。無料で複数取得できるので、戸籍原本を提出したくない場合に活用すると良いでしょう。
相続人間の情報共有不足が招くトラブル
さらに、相続人間の情報共有不足が招くトラブル防止も重要です。一人の相続人が単独で申告手続きを進めていると、他の相続人が内容を把握できず不信感を抱く可能性があります。特に財産目録の内容や評価額、適用特例などについて十分な説明がないまま申告が終わってしまうと、後から「そんな財産聞いてない」「もっと節税できたのでは?」といった不満・トラブルに発展しかねません。そうした事態を避けるためにも、相続人全員で情報を共有しながら進めることが大切です。必要に応じて、間に税理士などの専門家を入れて説明してもらうのも有効でしょう。専門家が第三者の立場で関与することで、相続人間の納得感が高まりトラブル防止につながるケースもあります。
精神的・時間的な負担
最後に、精神的・時間的な負担も軽視できません。慣れない相続手続きを限られた期間で完了させるのは、思った以上に骨の折れる作業です。ご家族を亡くされた直後で精神的に大変な時期に、複雑な税金計算や書類作成に取り組むのは大きなプレッシャーとなるでしょう。無理をして体調を崩したり本業に支障をきたしては本末転倒です。「費用を節約したい」という思いは大切ですが、不安が大きい場合には無理をせず専門家に相談し、サポートを受けながら進める選択肢も検討してください。
税理士に依頼するメリット
相続税申告を税理士など専門家に依頼することには、多くのメリットがあります。主なものを見ていきましょう。
適切な節税アドバイスが受けられる
税理士に相談すれば、各種控除や特例の適用漏れを防ぎ、節税策を最大限活用した申告書を作成してもらえます。例えば、配偶者控除や小規模宅地特例、二次相続を見据えた分割の工夫など、素人では見落としがちなポイントまで考慮したアドバイスが期待できます。専門家ならではの視点で税額を減らす提案を受けられるのは大きなメリットです。また、節税だけでなく将来のトラブル防止や分割の仕方についても助言が得られ、総合的に安心できる対策を講じられるでしょう。
面倒な手続きや書類作成を任せられる
相続税申告には膨大な書類作成と税務手続きが伴いますが、専門家に依頼すればその大部分を代行してもらえます。財産評価の計算、申告書への転記や整理、税務署への提出など、煩雑な作業から解放され、時間と労力を大幅に節約できます。特に平日に役所や税務署に何度も出向く必要がなくなるため、お仕事をされている方にとっては非常に助かるでしょう。専門家がスケジュール管理も行ってくれるため、申告漏れの不安も軽減します。精神的な負担も和らぎ、安心して手続きを終えられるのは大きな利点です。
税務調査への対応も安心
相続税の申告後、税務署から税務調査が行われるケースがあります。専門家に依頼していれば、調査が入った際の立ち会いや回答も税理士が代理対応してくれます。税務署とのやり取りを専門家に任せられることで、依頼者自身は落ち着いて結果を待つことができます。万一申告内容に疑問が指摘されても、税理士が適切に説明・交渉してくれるため、追徴リスクの軽減や特例適用の主張もスムーズです。調査対応を一任できる安心感は、プロに依頼する大きなメリットと言えるでしょう。
こうしたメリットから、実際に相続税申告を税理士に依頼する人の割合は約86%にのぼるとのデータもあります(令和4年度財務省調査)。相続税申告は一生に何度も経験するものではなく、多くの方にとって初めて直面する複雑な手続きです。プロのサポートを得ることで、安心感や時間の節約はもちろん、最適な節税につながるケースも多いため、多くの人が専門家に依頼しているのです。
専門家に依頼する際の費用と選び方
税理士報酬相場
専門家に相続税申告を依頼する場合、気になるのが費用(報酬)です。一般的に、相続税申告業務の税理士報酬は「遺産総額の0.5~1%程度」が相場と言われています。例えば遺産総額が1億円あるケースなら、税理士報酬は約50万円~100万円ほど、5,000万円なら25万円~50万円ほどが目安です。ただし、遺産に不動産が多い場合や相続人が多数で手続きが複雑な場合、あるいは税務調査対応まで含めて依頼する場合などは加算料金が発生し、報酬額が1%を超えることもあります。逆に、たとえ遺産が少額でも一定額以上の費用がかかる場合もあります(相場として20~30万円前後の最低料金を設定しているケースが多いようです)。
依頼時の注意点
費用の支払いについて、相続人間で誰が負担するかを事前に話し合っておくと良いでしょう。一般的には相続財産から支払うケース(遺産から税理士費用を差し引いて残りを分配する)が多いですが、各相続人が按分して負担する方法でも構いません。いずれにせよ、後から揉めないよう全員の合意を取っておくことが望ましいです。
税理士報酬の料金体系は事務所によって様々です。遺産額に比例した定率報酬のところもあれば、最低一律料金+遺産額に応じた加算のところ、また成功報酬型(減額できた税額の◯%を成功報酬として後日支払う等)を採用している事務所もあります。成功報酬型は人によっては割高になるケースもあるため注意が必要です。最初の問い合わせ時や無料相談の段階で、料金体系が明瞭か、追加料金の有無、税務調査対応費用や相談料が別途かかるか等、不明点はしっかり確認しましょう。契約後に「聞いていなかった追加料金」が発生する恐れもありますので、可能であれば見積書を出してもらい納得した上で依頼すると安心です。
税理士の選び方
次に、税理士の選び方です。相続税は専門性が高いため、相続税に強い税理士を選ぶことが肝心です。具体的には、相続税申告の実績が豊富な事務所や、資産税(相続・贈与)を専門に扱う税理士法人などが信頼できます。初回無料相談を行っている事務所も多いので、気になるところを2~3社比較してみるのも良いでしょう。相談の際は「土地評価減についてどの程度提案してくれそうか」「こちらの希望をしっかり聞いてくれるか」など、相性や説明の分かりやすさも判断材料になります。相続税申告は一度きりの大切な手続きですから、信頼できる税理士を選ぶことが成功への近道です。
依頼するか迷っている方へ
最後に、自分で申告するか専門家に依頼するか迷っている方への助言です。総じて、「費用を節約してでも自分でやり遂げたいか」それとも「費用をかけても安全に任せたいか」という軸で考えると判断しやすいかもしれません。
相続税申告はやり直しがきかない一度きりの手続きです。不安が大きい場合には無理をせず専門家に相談し、安心して大切な相続手続きを完了させましょう。
相続税申告のご相談は名古屋市家族信託・相続の相談所へ
相続税申告を自分で行う場合のポイントと、税理士に依頼する利点についてご紹介しました。名古屋市家族信託・相続の相談所では、相続税申告を自力で進めるべきか専門家に任せるべきか悩まれている方に向けて、初回無料相談を実施しております。名古屋市エリアに特化した経験豊富な税理士が、ご家庭の状況に応じた最適な進め方をアドバイスいたします。自分で対応する場合のチェックポイントから、専門家に依頼する場合の費用見積りまで、お気軽にお問い合わせください。専門家のサポートを活用し、安心・確実に相続税申告を終えましょう。