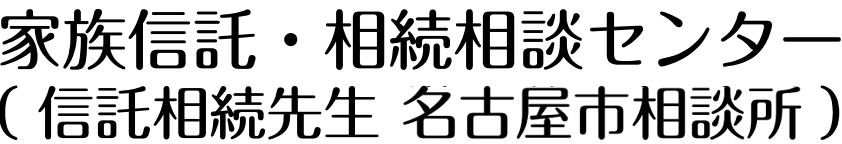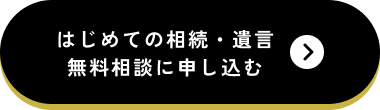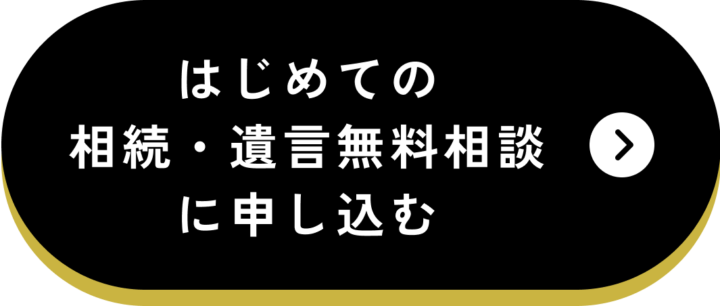相続税申告は誰に必要?基礎控除額と申告期限、手続きの流れ
- 公開日:
- 更新日:
高齢の親を持つ方にとって、親の相続が発生したとき相続税申告が誰に必要かは大きな疑問です。本記事では、相続税の基礎控除額という非課税枠を超える場合に誰が申告義務を負うのか、申告期限(死亡から10か月以内)の重要性と具体的な手続きの流れについて、名古屋の専門家が平易に解説します。また、申告に向けて準備すべき必要書類や財産評価のポイント、万一申告が遅れた場合の延滞税・加算税などペナルティについても触れます。相続税申告の基本をしっかり確認し、将来に備えましょう。
相続税申告が必要となるケース(申告義務の有無)
相続税の申告が必要か否かは、遺産総額が基礎控除額という非課税枠を超えるかどうかで決まります。基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円 × 法定相続人の数」です。例えば法定相続人が配偶者と子1人の計2人であれば、基礎控除額は3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。遺産総額(プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた正味の遺産額)がこの4,200万円を超える場合、原則として相続税の申告と納税が全相続人の連名で必要になります(逆に言えば、遺産が基礎控除内に収まれば相続税はかからず申告も不要です)。
注意すべきは、実際に税額が生じるかどうかに関わらず、遺産総額が一度でも基礎控除額を超えれば申告義務が発生する点です。例えば配偶者が相続する場合には、配偶者控除(配偶者に対する税額軽減)によって取得財産のうち1億6,000万円までは相続税がかからなくなります。この特例で最終的な税額がゼロになるケースでも、遺産総額が基礎控除を超えていれば一度申告書を提出する必要があります。同様に、生命保険金には法定相続人1人あたり500万円の非課税枠がありますが、それを使って結果的に税額0円になった場合でも、基礎控除を超える遺産を取得していれば申告は必要です。つまり「税金を払う必要があるか」と「申告が必要か」は別問題ということです。
近年(平成27年以降)は基礎控除額の引き下げにより、相続税申告が必要となる家庭が増加しました。全国平均では相続税が課税される被相続人は亡くなった方全体の約1割ですが、都市部である名古屋市では不動産評価が高い地域も多く、相続税が発生するケースが決して珍しくありません。例えば名古屋市内に土地付きの自宅を所有している場合、評価額によっては基礎控除額を超えて相続税申告が必要になることがあります。おおよその財産総額を把握し、「自分の家庭は申告が必要かどうか」を早めに確認しておくことが大切です。
なお、相続税の申告は被相続人ごとに1つの申告書を提出する形で行います(相続人全員の連名で1通の申告書を提出)。申告書には各相続人の取得財産や税額計算の明細を記載し、相続人全員が署名押印して提出します。各人で別々に申告する必要はなく、基本的には代表者が一括して申告する流れになります。
相続税申告の期限と手続きスケジュール
相続税申告の申告書提出期限は、被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。例えば1月15日に死亡した場合、その年の11月15日が申告期限となります。10か月という期間は一見長いようですが、実際には遺産整理や書類集めに追われてあっという間に過ぎてしまいます。特に不動産の評価計算や相続人間の調整に時間がかかるケースでは、早め早めの行動が求められます。
ここでは、相続発生から申告・納税までの一般的な手続きの流れを段階ごとに解説します。スケジュールを立てる際の参考にしてください。
相続人の確定と遺産全体の把握
まず誰が相続人になるのか確定します。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続人を調査しましょう。併せて遺言書の有無も確認します。並行して、被相続人が残した財産と負債をすべて洗い出し、財産目録(遺産目録)を作成します。現金・預貯金、株式・投資信託などの有価証券、不動産(土地・建物)、自動車、貴金属・骨董品、さらには死亡保険金や死亡退職金など相続で取得する財産も含め、プラスの財産を漏れなくリストアップします。負債(借入金残高や未払い税金・医療費、葬儀費用など)も忘れずに計上します。これによって遺産の全体像と正味の遺産額を把握でき、後の相続税額の試算に役立ちます。
※被相続人から相続人へ死亡前3年以内に贈与された財産や、相続時精算課税制度を適用して生前贈与された財産がある場合は、それらも相続財産に加算される点に注意が必要です(2024年以降の贈与については持ち戻し対象期間が死亡前7年以内に延長されています)。また、被相続人が遺言書を残していた場合はこの段階で内容を確認し、記載に沿って遺産分割や遺産計上を検討します。
各財産の評価額算出と相続税額の試算
財産目録ができたら、次に各資産の相続税評価額を計算します。預貯金は残高がそのまま評価額になりますが、不動産は相続税独自の評価方法(例:路線価や固定資産税評価額にもとづく計算)によって評価します。株式や投資信託も所定の方法で評価し、すべてのプラスの財産評価額の合計からマイナスの財産を差し引いた正味の遺産額を算出しましょう。正味遺産額が出せたら、それが基礎控除額内に収まるかどうか確認します。例えば法定相続人が配偶者と子1人の合計2人なら基礎控除額は4,200万円です。この額を超える遺産がある場合には相続税申告が必要となります。
課税対象となる場合、続いて相続税額の試算を行います。相続税の税率は累進課税(課税額が大きいほど税率も高くなる方式)で10%から最大55%まで段階的に定められています。実際の計算は法定相続分に応じて各相続人ごとの税額を計算し、最後に実際の取得分で按分し直す少し複雑な方法です。自分で正確に計算するのは難しいため、国税庁HPの「相続税の申告書作成コーナー」などシミュレーションツールを利用するとよいでしょう。なお、配偶者控除や小規模宅地特例などを適用すれば税額がゼロになるケースでも、前述のとおり遺産総額が基礎控除を超えている場合は申告を省略できません。
遺産分割協議と申告書類の作成
相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するか合意します(遺言書がある場合は基本的にその内容に沿って分けます)。協議が整ったら、相続人全員の実印を押した遺産分割協議書を作成します。次に、相続税の申告書を税務署所定の様式で作成します。申告書には主な第一表のほか、財産の種類ごとに明細を記載する第二表以降の用紙(土地や有価証券の明細、債務控除の明細など複数の附表)があり、必要事項を漏れなく記入します。作成にあたっては、以下の書類を添付します。
- 被相続人の戸籍関係書類一式(被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍、相続人全員の戸籍謄本)
- 被相続人の住民票の除票、相続人全員の住民票(マイナンバーが記載されたもの)
- 財産の内容を証明する書類(預貯金の通帳コピーや残高証明書、不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書、株式の取引残高報告書、生命保険金の支払通知書など)
- 債務や葬儀費用を証明する書類(借入金残高証明書、医療費や葬儀費用の領収書 など)
これら必要書類をすべて揃え、相続税申告書に添付して提出します。提出先は被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。提出方法は税務署窓口への持参または郵送で行えます(近年では国税庁の電子システムe-Taxでも提出可能です)。相続税申告書の提出期限は繰り返しになりますが被相続人死亡から10か月以内です。
税務署へ申告書提出・納税
税務署に相続税申告書類一式を提出します。申告書提出と同じ期限までに、計算した相続税額を納税します。納付は現金で金融機関から行うほか、e-Taxを利用したダイレクト納付やインターネットバンキング納付、ATM納付なども可能です。申告期限と納期限は同じ日であり、納税まで完了して初めて正式な手続き完了となります。万一お金が足りず期限までに全額納付できない場合でも、申告書だけは期限内に提出し、可能な限り納税した上で後述する延納の申請を行うことが肝心です。
以上が相続税申告までの一般的な流れです。名古屋市などでは、相続発生から半年程度が経過すると税務署から「相続税申告のお知らせ」や「お尋ね」の文書が届くことがあります。これは「申告期限が近づいていますが大丈夫ですか?」という確認の意味合いで送られてくるものです。この段階でまだ申告準備に着手できていないと非常に慌ただしくなるでしょう。理想的には死亡後すぐ(遅くとも数か月以内)に動き始めるのが望ましいと言えます。もし遺産分割協議がまとまらず10か月以内に分配方法が決めきれない場合でも、法定相続分どおりに仮に分割したものとして申告書を提出し、後日協議成立後に修正申告するという方法もあります。とにかく期限内に申告書を提出し納税も済ませることが何より重要です。
納税が難しい場合の延納制度・リスク
相続税額が大きく、一度に現金で納めるのが難しい場合、条件を満たせば延納(えんのう)制度と呼ばれる分割納付の制度を利用できる可能性があります。延納を利用すると、相続税を何年間かに分けて分割払いすることが認められます。ただし誰でも簡単に使えるわけではなく、利用には次のような条件があります。
- 期限内申請: 延納を希望する場合、相続税申告書の提出期限までに所定の延納申請書を税務署に提出する必要があります。申請期限は申告期限と同じく死亡から10か月以内です。
- 相続税額が10万円超: 延納は相続税額が10万円を超える場合にしか認められません。税額が少額のときは延納できず、一括納付が原則です。
- 金銭一括納付が困難: 相続税を一度に現金で納めるのが難しい事由が必要です。例えば「遺産の大部分が不動産で、すぐに現金化できないため一括納付が困難」といったケースです。
- 担保の提供: 延納税額に見合う担保を原則として提供しなければなりません(相続税額が100万円以下かつ延納期間3年以下の場合は担保不要)。
延納が許可されると、不動産の割合などに応じて最長5年から20年の分割払いが認められます。不動産の占める割合が大きいほど長期間(最大20年)にわたって延納できます。ただし、延納期間中は利子税という延滞利息に相当するものが課されます。延納の利子税率は延納期間の長さや金利情勢によって異なりますが、概ね年1.2%~6.0%程度の範囲で設定され、長期の延納になるほど上限6%程度の高めの利率が適用されます。延納を利用するときは、この利子負担も踏まえて本当に延納すべきか検討する必要があります(場合によっては銀行から借り入れて一括納付した方が負担が少ないケースもあります)。
万が一延納の許可を受けていても、計画通り納税できなくなれば「物納」への切り替え申請も可能です。物納とは、不動産や有価証券などの現物で納付する制度で、延納でも支払えない税額がある場合の最終手段です。物納が認められるためには、延納によってもなお金銭納付が困難であること、物納に充てる資産が国が定める条件(換金性や適格資産の種類など)を満たすことなど、非常に厳格な要件があります。例えば物納可能な資産は基本的に不動産や国債などに限られ、しかも申請は相続税の申告期限から10年以内に行う必要があります。物納はあくまで延納でも支払えない残額がある場合の救済措置と考え、基本は期限内に現金で納付することを目指しましょう。
延納や物納は最後の手段と心得て、まずは期限内完了を最優先に進めることが肝心です。どうしても資金繰りが厳しい場合でも、「申告書だけは期限内に提出する」「ある程度納税して延納申請する」など、なんとか期限内に手続きを取る姿勢が重要になります。延納や物納の必要が出てきそうなときは早めに税理士に相談し、適切な申請手続きを進めましょう。
申告をしなかった場合のペナルティ
相続税の申告が必要にもかかわらず申告しなかったり、期限後に提出したりすると、延滞税や無申告加算税といったペナルティ(加算税)が課されます。延滞税は本来の納期限(死亡後10か月の翌日)を過ぎてから完納するまでの日数に応じて課される利息のようなもので、年利14.6%(一部期間は年7.3%)を基準に日割り計算されます。無申告加算税は期限までに申告書を提出しなかったことに対する罰則税で、本来納めるべき税額の5~15%が課されます(自主的に期限後申告すれば5%、税務署から指摘を受けると10%、悪質な場合は20%)。さらに、意図的に財産を隠したり虚偽の申告をした場合は、重加算税として35~40%もの厳しい罰則税が科されることもあります。
また、期限後申告や無申告だった場合、適用できるはずだった各種特例が適用困難になったり、税務署からの印象も悪くなることが考えられます。例えば、被相続人が居住していた宅地の評価額を最大80%減額できる小規模宅地等の特例は期限内申告が適用要件となっているため、申告が遅れるとこの特例が使えなくなってしまいます。その他、配偶者控除の適用や各種税額控除についても、期限内申告が要件となっているものがあります。期限厳守が鉄則であり、無申告で放置していると後から大きな不利益を被る可能性が高いのです。
仮に申告を忘れていて期限が過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く自主的に申告することが大切です。税務署は不動産の名義変更情報や銀行口座の残高移動などから相続財産を把握しており、いずれ税務調査や問い合わせが来る可能性が高いと考えましょう。無申告のままですと、調査によって発覚した際に重加算税まで含め多額の追徴を受けるリスクがありますし、家族にとっても後味の悪いトラブルとなりかねません。期限内に正しく申告・納税を済ませることが、相続税の円満な完了につながるのです。
相続のご相談は名古屋市家族信託・相続の相談所へ
本記事では相続税申告の基本について解説しました。名古屋市家族信託・相続の相談所では、相続税申告や相続対策について専門の税理士がご相談に応じます。初回のご相談は無料ですので、相続税申告が必要かどうか分からない場合や手続きに不安がある場合も、お気軽にお問い合わせください。名古屋市エリアの皆様の大切な相続手続きを、専門家の視点で丁寧かつ的確にサポートいたします。