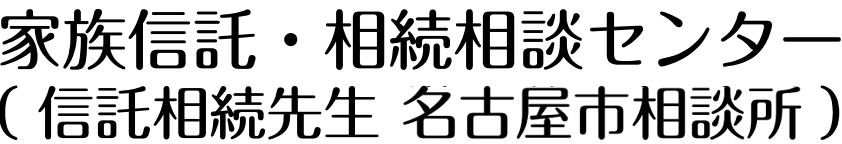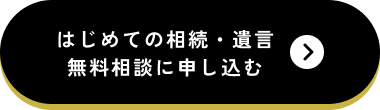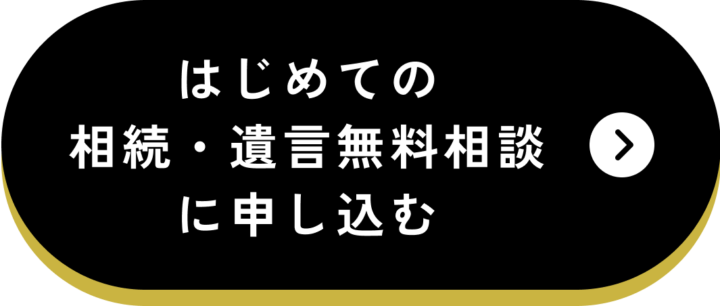生命保険や不動産活用は相続税対策になる?その他の節税策と注意点
- 公開日:
- 更新日:
相続税の負担を減らすため、生命保険の非課税枠や不動産の活用など、さまざまな相続税対策が検討されます。それぞれ本当に節税に効果があるのか、気になる方も多いでしょう。
本記事では、生命保険や不動産を使った方法はもちろん、借入金の活用や二次相続まで見据えた対策についても解説します。各対策のメリットとデメリット、注意すべき点を、名古屋市家族信託・相続センターの専門家がわかりやすく説明します。
生命保険を活用した相続税対策
まずは生命保険を活用した相続税対策です。生命保険は、受け取った死亡保険金に特別な非課税枠があるため、上手に使えば相続税の負担を軽減できます。また、契約の仕方によっては、保険金を相続税ではなく所得税の課税対象とする工夫も可能です。
死亡保険金の非課税枠の活用
生命保険には「法定相続人1人あたり500万円まで非課税」という優遇措置があります。たとえば法定相続人が妻と子2人の合計3人いれば、死亡保険金から最大1,500万円までが相続税の課税対象になりません。現金で遺すよりも保険金として受け取った方が、その分だけ相続税を減らせることになります。基礎控除(※)とは別枠の非課税枠ですので、一定以上の資産があるご家庭では大きな節税効果を期待できます。(ただし、死亡保険金の受取人が法定相続人以外の場合は非課税枠が適用されない点に注意が必要です。)
(※相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数。これは生命保険の非課税枠とは別に差し引ける枠です。)
所得税が適用される契約形態の工夫
通常、被保険者本人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は相続財産として扱われます。しかし契約の仕方によっては、所得税(一時所得)や場合によっては贈与税の課税対象とすることも可能です。保険料の負担者(支払う人)と保険金の受取人を同一人物にすると、死亡保険金は相続税ではなく一時所得として所得税の課税対象になります。具体的には、子どもが親の生命保険料を負担し、子ども自身を受取人とする契約形態などが該当します。
一時所得として受け取る場合、保険金からそれまで支払った保険料総額を差し引いた残額が利益とみなされ、さらに50万円の特別控除が適用されます。その上で、その利益の2分の1だけが課税対象となるため、最終的に相続税よりも低い負担で済むケースもあります。ただし、保険金が大きな臨時収入になると受取人の課税所得が増え、もともとの収入次第では高い税率が適用されて逆効果となる可能性もあります。所得税と相続税のどちらが有利かは金額や相続人の収入状況によりますので、事前に専門家にシミュレーションしてもらうと安心です。なお、契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の三者すべてが異なるケースでは死亡保険金は贈与税の対象となります。贈与税は非課税枠が小さく税率も高いため、この契約形態は通常避けるべき点も覚えておきましょう。
不動産の活用による相続税対策
次に、現金ではなく不動産で資産を保有することで相続税評価額を下げる対策です。不動産は評価方法の違いにより、同じ金額の資産でも現金よりも低い評価額で相続財産として計上できる場合があります。また、賃貸用の不動産を持っていると評価額がさらに下がる仕組みや、一定の条件下では評価額を大幅に減らせる特例制度もあります。
現金より不動産の方が評価が低くなる仕組み
相続税では現預金や株式などは基本的に額面(時価)どおりの評価となりますが、不動産については路線価や固定資産税評価額にもとづいて評価するため、市場価格より低い価額になるのが一般的です。一般的に、土地は時価の約80%、建物(家屋)は時価の約70%程度の評価になると言われています【※】。この仕組みを利用し、生前に現金で土地や建物を取得しておけば、同じ資産額でも相続の際に評価額を抑え、結果として相続税の節税につながります。例えば、現金1億円で購入した不動産が相続税評価では7,000万円となるケースでは、それだけ課税対象額が減少するわけです。特に都市部の土地は時価が高い分、路線価評価との差による圧縮効果も大きくなり得ます。名古屋市内で不動産をお持ちの場合も、こうした評価額の違いが節税に寄与する可能性があります。
【※補足】路線価は国税庁が定める土地評価額で、時価(実勢価格)の8割程度が目安とされています。建物の評価に使われる固定資産税評価額は時価の7割程度が目安です。地域や物件によって差はありますが、一般的な目安として覚えておくと良いでしょう。
賃貸物件や小規模宅地特例の活用
不動産の相続税評価額をさらに下げる方法として、賃貸物件の活用が挙げられます。賃貸アパートや貸家付きの土地は、自用の不動産に比べて評価額が低く計算されます。第三者に貸していることで所有者が自由に使えない分、評価を差し引く仕組みがあるためです。例えば建物は、賃貸用であれば評価額が約30%減額されます(借家権割合による減額)。土地についても、賃貸物件が建っている土地(貸家建付地)は、借地権割合と借家権割合を乗じた分だけ評価額が圧縮されます。地域にもよりますが、土地評価額がさらに2〜3割程度下がるケースも多く、賃貸物件を持つことで一層の節税効果が期待できます。
さらに、被相続人が居住していた宅地や事業用・貸付事業用の宅地については、小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。この特例を使うと、一定の面積までの土地の相続税評価額を大幅に減額することが可能です。例えば、被相続人が自宅として使っていた土地(特定居住用宅地等)であれば最大330㎡まで評価額を80%減額、賃貸事業のための土地(貸付事業用宅地等)であれば最大200㎡まで50%減額といった大きな優遇が受けられます。要件を満たせば非常に強力な節税策ですが、適用条件が細かく定められているため、実際に使えるかどうかは専門家と確認しながら検討する必要があります(例えば、同居親族が相続後もその家に住み続けること、といった要件がありますので注意してください)。
借入金を使った相続税対策の考え方
資産運用や不動産購入の際に借入金(ローン)を活用することも、相続税対策として考えられる手法の一つです。あえて借入を行うことで相続時の純資産額(資産から負債を引いた額)を圧縮し、結果的に課税対象を小さくする狙いがあります。ただし、借入には当然リスクも伴うため、メリットとデメリットを正しく理解しておくことが重要です。
あえて借入をして純資産を圧縮する方法
通常、相続税は残された純資産(総資産-負債)に対して課税されます。そこで、生前にあえて借入をして資産を購入すると、相続時点ではその借入金が負債として控除され、結果として純資産額が減少します。
特に不動産投資などでローンを組むケースが代表的です。例えば、手元の現金5,000万円と銀行借入5,000万円を合わせて1億円の収益物件を購入した場合、相続時にはその不動産の評価額が7,000万円になり、借入金5,000万円を差し引けば純資産は2,000万円分に圧縮される計算になります。現金で1億円を持っていた場合に比べ、課税対象を大幅に減らせるわけです。
このように、ローンを活用して資産を取得すれば、資産自体の評価減効果(前述の不動産評価圧縮)と負債計上による効果で、相続財産を抑えることが可能です。特に多額の現金を保有している場合には、有効な節税策の一つとなり得ます。また、購入した不動産から家賃収入が得られれば、生前のローン返済に充てつつ資産形成ができる点もメリットと言えるでしょう。
借入のリスクと注意点
もちろん、借入金を利用する節税策にはリスクも伴います。ローンを組めば毎月の返済や利息支払いが発生し、被相続人やご家族の生活に負担となる可能性があります。高齢の方が大きな借金を抱えたまま亡くなった場合、残された家族が返済を引き継がなければなりません。相続財産が不動産中心で現金が少ないと、借金の返済資金に困る恐れもあります。
さらに、不動産投資で借入を利用した場合、物件の価値下落や空室リスクも考慮しなければなりません。期待した節税効果が得られないばかりか、ローンだけが残る事態にもなりかねません。加えて、住宅ローンには団体信用生命保険(団信)が付帯し、債務者が死亡するとローン残高が保険によってゼロになる仕組みがあります。この場合、相続時に負債が残らず純資産を圧縮できなくなるため、節税策としては無意味になってしまいます。借入を節税目的で利用する際は、こうしたリスクやローンに付随する保険の扱いにも注意が必要です。
このように、借入を利用した節税策は計画的に行わなければ、かえって家族に負担や危険を残す可能性があります。返済計画を十分に立て、無理のない借入額にとどめることが大切です。
二次相続を見据えた対策
相続税対策を考える際には、二次相続(両親のうち二人目が亡くなったときの相続)まで踏まえた視点も重要です。一次相続(最初の親の相続)だけの節税にとらわれると、その後の二次相続で予想外に大きな税負担が生じることがあります。両方のバランスを考えた遺産分割や保険金の活用がポイントとなります。
一次相続と二次相続をバランスよく設計する
最初に配偶者が亡くなる一次相続では、配偶者控除という強力な非課税制度があります。配偶者が相続する財産には、法定相続分相当額までか1億6,000万円まで(いずれか多い方)相続税がかからないため、一次相続では配偶者がすべて相続して税額ゼロにできるケースも多いです。
しかし、配偶者が財産を全て引き継いだ結果、次の二次相続(残された配偶者が亡くなったとき)では、相続財産に対して配偶者控除が使えず、子どもたちが高額の相続税を支払うことになりがちです。一次相続と二次相続を通じたトータルで見ると、かえって税負担が増えてしまう場合もあります。
そこで、一次相続の時点で配偶者以外の相続人(子など)にもある程度財産を分配し、納税を平準化する方法が検討されます。あえて一次相続でいくらか相続税を払い、二次相続での課税額を減らすイメージです。例えば、父親が亡くなった際に母親だけでなく子どもにも遺産を分けておけば、父の相続では多少の税金が発生するものの、母親に集中していた資産が減るため、その後母親が亡くなったときの相続税負担を抑えられる可能性があります。
実際にどの程度分配すれば有利になるかは遺産額や相続人の構成によって異なります。一見複雑ですが、一次相続の段階から専門家に相談しシミュレーションすることで、二次相続まで見据えた最適な遺産分割のプランを検討できます。ご家族の生活保障と税負担軽減のバランスを考え、計画的に設計することが大切です。
生命保険契約で非課税枠を分散させる方法
一次・二次相続のバランス調整において、生命保険は有効なツールになります。死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を一次相続と二次相続の両方で活用することで、トータルの節税効果を高められるからです。
例えば、父親(一次相続の被相続人)の死亡保険金を子どもが受け取るよう契約しておけば、父親の相続時に「法定相続人の数×500万円」の非課税枠を最大限活用できます(法定相続人が妻と子2人なら最大1,500万円まで非課税)。次に母親(二次相続の被相続人)が亡くなる際にも、母親を被保険者とした生命保険から子どもが保険金を受け取れば、再度「500万円×子の人数」の非課税枠を使うことができます。つまり、夫婦それぞれの相続で保険金の非課税枠を二重に活用できるわけです。
このように生命保険を活用すれば、配偶者に全て遺産を集中させた場合に比べて子世代へ早めに財産を移転できるため、二次相続時の税負担を大きく減らす効果が期待できます。一次相続では配偶者控除によって税額ゼロであっても、生命保険金を使って子へ現金を残しておけば、結果的に二次相続時の課税財産を減らすことができます。また、生命保険金は受取人ごとに支払われるため、相続人間で資金を分けやすく、遺産分割の実務上も役立ちます。
生命保険を二次相続対策に活用するには、契約者や受取人の設定を計画的に行う必要があります。ご夫婦それぞれで生命保険契約を用意し、受取人を子どもに指定しておく、といった工夫が有効です。家族構成や資産状況に合わせて保険契約を設計し、非課税枠を最大限に生かすことがポイントです。
節税策を講じる際の共通注意点
ここまで見てきた各種の節税策には、それぞれメリットがある一方、共通の注意点もいくつかあります。節税だけに気を取られて失敗しないよう、以下の点に留意しましょう。
流動性・維持費などの負担
節税策に伴う主なデメリットとして、次のような負担が考えられます。
- 流動性の低下: 資産を不動産や保険に振り替えると、手元の現金が減り資金の流動性が下がります。相続後に納税資金や遺産分割のための現金が必要になっても、すぐに用意できないリスクがあります。特に不動産は売却に時間がかかるため、急な出費に対応しづらくなる可能性があります。
- 維持コストの増加: 不動産を所有すれば固定資産税や管理費・修繕費が毎年かかり、生命保険を利用すれば長年にわたり保険料を支払い続ける必要があります。こうしたコストが累計で節税額を上回ってしまうと、対策を講じた意味がなくなってしまいます。例えば「相続税を減らしたけれど、生前に支払った保険料の総額の方が高くついた」というような本末転倒な事態も起こりえます。
- 利息負担: 借入金を使った場合、利息の支払いという負担も発生します。借入額が大きければ支払利息も増え、将来減らせる相続税額と比べて見合わない可能性があります。金利変動による支払額増加リスクも考慮が必要です。
本末転倒を避けるには
相続税対策はあくまで手段であり、節税そのものが目的になってはいけません。節税にこだわるあまり、本来守るべきご家族の生活や大切な財産が損なわれては本末転倒です。
例えば、「相続税を1円でも減らしたい」と無理に不動産投資を行い、ローン返済に追われて生活が苦しくなってしまっては意味がありません。また、多額の借金を残してまで税金を減らそうとするのも考えものです。極端な節税策はかえってリスクを高め、場合によってはご家族の間に不安や不満を残す結果にもなりかねません。
節税策はあくまで円満な相続を実現するための手段です。まずはご家族の将来の安心を最優先に考え、その上で適切な対策を選択するようにしましょう。対策ありきではなく、「なぜその対策をするのか」という目的を見失わないことが大切です。
相続税対策のご相談は名古屋市家族信託・相続センターへ
相続税対策には、生命保険の活用、不動産への資産組み換え、借入の利用、二次相続まで見据えた工夫など、さまざまな方法があります。それぞれ節税効果や適用条件が異なり、組み合わせ方によっても最終的な効果は変わってきます。大切なのは、ご家族の状況や資産構成に合った対策を選ぶことです。
闇雲に節税だけを追求するのではなく、将来の生活やご家族の安心を見据えてプランを立てましょう。
名古屋市家族信託・相続センターでは、相続税対策に関する初回無料相談を行っています。名古屋市および近郊で相続対策をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。経験豊富な税理士が、ご家族に最適なプラン作りを親身にお手伝いいたします。