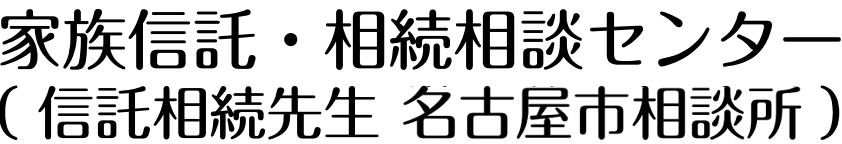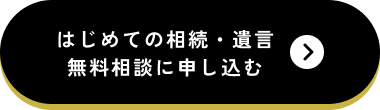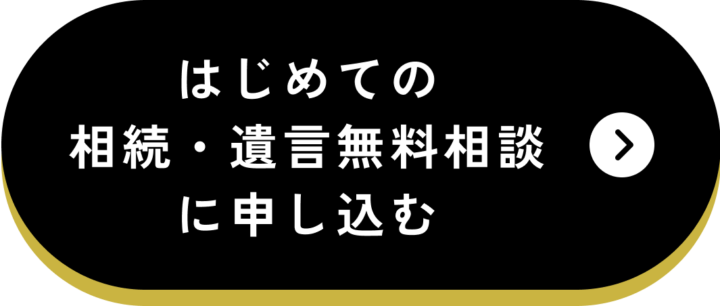生前贈与で賢く相続税対策:非課税枠の活用と注意点
- 公開日:
- 更新日:
親が生前に子や孫へ財産を贈与する生前贈与は、賢い相続税対策として注目されています。相続税は遺産総額に応じて課税されますが、生きているうちに財産を移しておけば、その分だけ相続発生時の課税対象が減り、将来の相続税負担を軽減できます。特に名古屋市のように不動産価値が高い地域では相続税が発生しやすいため、生前贈与による対策が重要になります。日本の税制には毎年110万円まで非課税で贈与できる暦年贈与や、一度に大きな額を移せる相続時精算課税制度などの仕組みがあり、上手に活用すれば大きな節税効果が期待できます。本記事では、高齢の親を持つ50代の子世代に向けて、生前贈与が相続税対策として有効な理由と具体的な活用法、さらに行う際の注意点を、名古屋市の事例や専門家の視点も交えてわかりやすく解説します。
生前贈与の基本と相続税対策としての意義
生前贈与で相続財産を減らし将来の税負担を軽減
生前贈与とは、文字通り生きているうちに自分の財産を子や孫など次世代に贈与することです。親が元気なうちに財産を移しておけば、将来親が亡くなった時点での相続財産が減り、その分相続税の課税対象も小さくなります。例えば、生前贈与を全く行わない場合と毎年非課税枠内で贈与を続けた場合では、最終的な相続税額に大きな差が出るケースがあります。ある試算では、20年間にわたり配偶者と子4人に毎年110万円ずつ贈与したところ、生前贈与をしなかった場合と比べて相続税が約1,300万円減少したとの報告もあります。長期にわたりコツコツと贈与を行えば、それだけ大幅な相続税の軽減につながる可能性があるのです。
相続人の数と贈与開始時期が節税効果を左右する
生前贈与による節税効果は、相続人(財産を受け取る人)の数や贈与を始めるタイミングによっても変わってきます。例えば相続人が二人(子が二人)いる場合、それぞれに年間110万円ずつ合計220万円を贈与しても贈与税はかかりません。受け取る人の数が多いほど毎年非課税で移転できる額の総計が増えるため、その分だけ早く相続財産を減らすことができます。一方、相続人が少ない場合は非課税で移せる総額も限られるため、より長い期間をかけてコツコツ贈与を続ける必要があるでしょう。
また、生前贈与はできるだけ早く開始することが重要です。高齢になってから慌てて多額の財産を贈与しても、それが亡くなる直前の3年以内(※2024年以降の贈与については段階的に7年以内まで延長)であれば、その贈与分は相続財産に持ち戻されて課税対象になってしまいます。いわゆる「駆け込み贈与」は節税にならないどころか、税務上は相続税逃れを防ぐための持ち戻し規定によって無効化されてしまうのです。逆に、若いうちから計画的に贈与を始めておけば、贈与から長い年月が経過した分は相続財産に加算されにくくなるため、相続税対策としての効果が高まります。実際、2024年の税制改正によって持ち戻し対象期間を最終的に7年へ延長することが決定し(延長された4~7年前の贈与については合計100万円まで加算免除となる緩和措置あり)、以前にも増して早めの贈与開始が求められるようになっています。
暦年贈与の活用と注意点(110万円非課税枠、名義預金・定期贈与リスク)
暦年贈与の仕組みとメリット
暦年贈与(暦年課税制度)とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産額に応じて贈与税を課す仕組みです。この制度では年間110万円までの基礎控除(非課税枠)が設けられており、その範囲内の贈与であれば贈与税がかかりません。110万円という枠は「受贈者一人あたり」に適用されるため、贈与を受ける相手の人数に制限はなく、資金の使い道にも特に制限がありません。つまり、誰に対して何の目的で贈与しても、各人につき毎年110万円までは非課税で渡せる非常に使い勝手の良い制度です。暦年贈与のメリットは、長期間にわたって財産を少しずつ移転できる点にあります。例えば子や孫など複数の家族に毎年110万円ずつ贈与すれば、一年間で数百万円規模の資産を無税で次世代に移すことも可能です。年数を重ねれば累計で数千万円単位の財産を贈与税ゼロで承継できるため、富の生前承継手段として広く利用されています。
暦年贈与を活用する際の注意点
暦年贈与を効果的かつ安全に活用するため、以下のポイントに注意しましょう。
- 毎年ごとに贈与契約書を交わす: 贈与の都度、贈与者(親)と受贈者(子)が合意した証拠として贈与契約書を作成しておきます。書面がないと「本当に贈与が行われたのか」が後から証明できず、税務署に贈与が否認されるリスクがあります。日付や金額、贈与の意思を明記した契約書を取り交わし、確実に証拠を残しましょう。
- 「○年間毎年110万円」のような定期贈与にしない: 最初から「毎年○万円ずつ○年間贈与する」といった計画を立てると、税務署に定期贈与と見なされる恐れがあります。一度にまとまった額を贈与する約束と判断され、その合計金額に対して贈与税が課税されかねません。贈与額や時期は毎年その都度決め、契約書も毎年別々に作成して、あくまで単発の贈与を繰り返している形をとりましょう。
- 名義預金に注意し確実に受贈者へ渡す: 親が子名義の口座に内緒で振り込むだけでは、子が贈与を受けた事実を知らず契約が成立していないため、その預金は名義だけ子の名義預金と判断されてしまいます。そうなると移した資金は結局親の遺産とみなされ相続税の課税対象になります。避けるためには、贈与は現金手渡しより銀行振込で行い、振込記録や通帳を保管しておきます。また契約書にも「○年○月○日に○○銀行口座に○円を振込んだ」旨を記載し、贈与の事実を明確に残しましょう。
- 贈与者自身の生活資金を確保しておく: 生前贈与で財産を渡しすぎて、贈与者本人の老後資金が不足しては本末転倒です。無理のない金額とペースで贈与することが大切になります。贈与計画を立てる際は、自分の生活に支障が出ない範囲かどうか、必要に応じて税理士など専門家に相談しながら検討しましょう。
相続時精算課税制度の活用(概要、メリット、2024年改正点、注意点)
相続時精算課税制度の概要とメリット
相続時精算課税制度とは、生前にまとまった額を贈与できる仕組みで、主に60歳以上の親・祖父母(贈与者)から18歳以上の子・孫(受贈者)への贈与に適用できます。最大の特徴は、累計で2,500万円までの贈与であれば贈与税がかからない点です。極端な例を言えば、2,500万円までなら一度にまとめて子や孫に渡しても贈与税は0円になります。
この制度を使えば、生前に一気に多額の財産を移転できるため、子世代が早い段階で資金を有効活用できるメリットがあります。例えば、親が高齢になる前に住宅購入資金や事業資金を子に援助したい場合などに有効でしょう。ただし相続時精算課税は「相続時に精算する」仕組みであり、贈与した財産は贈与者が亡くなった際に相続財産に合算して相続税を計算します。そのため贈与税は大幅に節約できますが、その分相続税が完全になくなるわけではない点に注意が必要です。
しかし、価値が将来上がりそうな財産を早めに贈与しておくことで節税効果が期待できます。贈与した財産は相続時には「贈与時の評価額」で遺産に加算されるため、贈与後に値上がりしても増加分にかかる相続税を抑えられる可能性があるからです。例えば、地価が上昇しそうな不動産や今後株価が上がる見込みの株式を生前に移しておけば、その値上がり分については相続税の課税対象から外せるでしょう。
2024年税制改正で拡充されたポイント
相続時精算課税制度は2024年の税制改正によって使い勝手が向上しました。従来、この制度を選択すると贈与税の基礎控除110万円(年間非課税枠)は適用されず、贈与額の全てが累計2,500万円の枠に算入されていました。しかし2024年1月からは、新たに年間110万円までの基礎控除枠が創設されています。これは2,500万円の特別控除枠とは別枠で、年110万円以内の贈与であれば贈与税も相続税の持ち戻しも発生しません。言い換えれば、相続時精算課税を選択中でも年間110万円までの贈与は暦年贈与と同様に非課税かつ相続財産にもカウントされないということです。この改正により、「基本は110万円以下の贈与を続け、必要なときに大きな額を一度に贈与する」といった柔軟な使い方が可能になりました。
相続時精算課税を利用する際の注意点
相続時精算課税を検討・利用する際には、以下のような点に注意が必要です。
- 一度選択すると暦年贈与に戻れない: 相続時精算課税は一度適用を選ぶと、同じ贈与者から受贈者への贈与は全てこの制度で課税される決まりです。途中で「やはり毎年110万円までの通常贈与に切り替えたい」と思っても元には戻せません。選択後は110万円以下の贈与でも毎回所定の贈与税申告が必要になるため、この制度を利用するかどうかは慎重に判断しましょう。
- 贈与の都度、忘れずに申告する: 相続時精算課税を利用して贈与を行った場合、その翌年に税務署へ贈与税の申告をする必要があります。たとえ贈与税が発生しない範囲内でも、所定の届出と申告を怠るとペナルティの対象です。特に初年度は「相続時精算課税選択届出書」を含めた申告が必要で、これを忘れると本来非課税にできた贈与に贈与税が課されてしまいます。例えば2,000万円を贈与したのに届出をしないままだと、暦年贈与と見なされ数百万円の贈与税が課税される事態にもなりかねません。
- 節税効果がないケースもある: 相続時精算課税は贈与税の大幅軽減がメリットですが、相続税自体の節税効果は限定的です。そのため、もともと相続税がかからない程度の資産規模であれば、この制度を使っても節税のメリットはありません。実際、税理士に相談すれば「お宅の場合は相続税が発生しない見込みなので相続時精算課税を使う必要はないでしょう」といった助言が得られるケースもあります。制度を利用すべきか迷う場合は、専門家の意見も参考に自分のケースで本当に有効か見極めることが大切です。
- 大口贈与ならではのリスクにも注意: 一度に大きな額を渡すと、贈与者本人の老後資金が減って生活に支障をきたす恐れがあります。また、特定の子にだけ多額の生前贈与を行うと、将来相続時に他の相続人との不公平感(特別受益の問題)が生じ、トラブルになる可能性もあります。相続時精算課税を利用する際は、税金面だけでなく家族全体のバランスや自分の生活への影響も踏まえて判断しましょう。
生前贈与における共通注意点(贈与契約書、記録管理、申告義務、駆け込み贈与)
贈与の事実を示す記録を残す
生前贈与を行う際は、贈与契約書や資金移動の記録をしっかり残しておくことが何より重要です。贈与する人ともらう人双方の合意が明確になっていないと、「実際には贈与がなかったのではないか」あるいは「子の名義で預けているだけで親の財産ではないか(名義預金)」と税務署に疑われる可能性があります。そうならないよう、贈与のたびに契約書を交わし、通帳の写しや振込明細などのエビデンスも保管しておきましょう。書面と記録が揃っていれば、後日万一税務調査が入っても生前贈与の事実を客観的に説明することができます。
駆け込み贈与は節税にならない
繰り返しになりますが、亡くなる直前にまとめて贈与する駆け込み贈与には相続税の節税効果がありません。法律上、被相続人の死亡前3年以内(2024年以降の贈与については段階的に7年以内まで)の生前贈与は相続財産に持ち戻して課税する決まりになっています。せっかく生前にお金を渡しても、死亡直前の贈与であれば相続税の対象から逃れられないということです(※延長された4~7年前の贈与については合計100万円まで加算しない緩和措置があります)。「余命がわずかだから今のうちに大金を渡せば相続税をゼロにできるだろう」という考えは通用しません。それどころか、不自然な時期の大口贈与は税務調査でも目を付けられやすく、後から修正申告や追徴課税を受けるリスクも高くなります。生前贈与による相続税対策を成功させるには、「いつ何が起こるか分からないので早めに少しずつ」が鉄則です。
贈与税の申告漏れに注意
生前贈与を活用する以上、贈与税の申告も正しく行う責任があります。暦年贈与で年間110万円を超える贈与を受けた場合や、相続時精算課税を利用した場合は、原則としてその翌年の2月~3月に所轄税務署へ贈与税の申告書を提出しなければなりません。申告すべき贈与を申告せず放置していると、いざ相続が発生した際や税務調査で発覚し、本来納めるより多くの税金や無申告加算税といったペナルティを課される恐れがあります。現金で手渡しすればバレないのではと考えるのは禁物です。税務署は預貯金の入出金や名義変更の情報から生前贈与を把握する術を持っており、申告漏れは高い確率で発見されます。実際、預金残高の変動などから過去の無申告の贈与が発覚し、複数年分の贈与税と加算税をまとめて納める羽目になったケースもあります。せっかくの生前対策が台無しにならないよう、贈与税の申告が必要な場合は期限内に確実に行いましょう。
仮想事例
名古屋市の親子で住宅資金を生前贈与した例
名古屋市在住の70歳の父親Aさんには、一人息子がいます。息子夫婦が名古屋で新居を購入するにあたり、Aさんは生前贈与で住宅購入資金を援助したいと考えました。まとまった金額を早めに渡す必要があるため、Aさんは税理士に相談のうえ相続時精算課税制度を選択し、息子に2,000万円を一括贈与しました。この贈与によりAさんに贈与税はかからず、息子はタイミングよく希望の住宅を購入できました。Aさんの将来の相続財産からはこの2,000万円が減少しますが、相続時には贈与時点の2,000万円が遺産に加算され相続税が計算されます。ただし、その後もし住宅の評価額が上昇していても、相続税の計算には贈与時の2,000万円が使われ、値上がり分については課税されません。結果的にAさんは、生前に息子の住居取得を支援するとともに、将来の相続税も一定程度抑えることができる可能性があります。なお、暦年贈与で毎年110万円ずつ援助する場合、2,000万円を贈与するには約18年かかってしまう計算です。相続時精算課税を活用したことで、Aさんは必要なときにまとまった資金を渡すことができ、息子も住宅取得のチャンスを逃さずに済みました。
専門家に相談すべき判断基準とメリット
生前贈与で専門家の助言が必要となるケース
生前贈与は各家庭の事情によって適切な進め方が異なります。次のような場合には、一度相続の専門家に相談してみることをおすすめします。
- 相続税がかかるかどうか自分では判断がつかない場合: 家族の資産総額が基礎控除額(※)を超えるか微妙なケースでは、まず専門家に相談して相続税対策が本当に必要かどうか見極めてもらうと安心です。
- 暦年贈与と相続時精算課税のどちらを選ぶべきか迷う場合: 家族構成や資産内容によって、どちらの制度を使うべきか判断が難しいこともあります。専門家に相談すれば、最新の税制改正も踏まえた上で自宅のケースに有利な方法をアドバイスしてもらえます。
- 贈与額や手続きが大きく専門知識が必要な場合: 何千万円もの贈与を検討している、大量の不動産や株式を移転したい、といった場合には、税務手続きも複雑になります。事前に税理士のサポートを受けることで、必要書類の準備や贈与税申告まで滞りなく進めることができます。
- 親が高齢で早急な対策が必要な場合: 親御さんが高齢で「いつ相続が発生してもおかしくない」状況では、持ち戻し期間の延長も踏まえて早急かつ適切な対策を講じる必要があります。限られた期間で最善の対策をとるためにも、専門家の力を借りることを検討すべきでしょう。
※相続税の基礎控除額 … 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(この金額までの遺産には相続税がかかりません)
専門家に相談・依頼するメリット
- 節税効果を最大化できる: 専門家は家族構成や資産状況を踏まえ、最も節税につながる贈与プランを提案してくれます。暦年贈与と相続時精算課税の使い分けはもちろん、場合によっては生命保険の非課税枠活用や家族信託の導入など他の対策も組み合わせ、トータルで相続税負担を減らす最適策を検討してもらえます。
- 手続きや書類作成を任せられる: 贈与契約書の作成や贈与税の申告書提出など、自分だけでは不安な手続きも専門家に依頼すれば安心です。税理士に依頼すれば税務署への申告漏れを防げますし、司法書士や行政書士と連携している事務所であれば贈与に伴う登記や契約書作成までワンストップでサポートしてもらえます。
- 最新の税制に基づいたアドバイス: 税制改正によるルール変更にも専門家は精通しています。2024年改正の新ルール(持ち戻し期間延長や110万円控除新設など)も踏まえ、最新の制度を最大限に活用した対策を提案してもらえるのは大きなメリットです。
- 心理的・時間的負担の軽減: 相続対策は自分たちだけで悩むと大きなストレスになりますが、プロに相談すれば不安が解消されます。手続きも任せられるためご家族の負担が減り、親御さんとの大切な時間を確保しながら計画を進めることができます。
まとめ
生前贈与は強力な相続税対策となり得ますが、正しい知識にもとづいて計画的に実行することが重要です。年間110万円まで非課税の暦年贈与は手軽で使いやすい一方、計画の立て方次第では非課税枠を活かしきれなかったり、定期贈与と見なされてしまうリスクがあります。相続時精算課税制度は大きな額を一度に移せるメリットがありますが、相続税の節税効果は限定的であり、利用には慎重な見極めが求められます。生前贈与を賢く活用するには、早めに対策を開始すること、そして贈与契約書の作成や記録管理・税務申告といった基本を怠らないことが肝心です。
また、生前贈与に適した具体的な方法や進め方は各家庭の状況によって異なります。今回解説した非課税枠の活用法や注意点を参考にしつつ、必要に応じて相続に強い税理士など専門家のアドバイスを取り入れることも検討しましょう。専門家と二人三脚で進めることで、ご家族にとって最適な生前贈与プランを安心して実行できるはずです。
相続のご相談は名古屋市家族信託・相続の相談所へ
名古屋市家族信託・相続の相談所では、生前贈与を含む相続対策について初回無料相談を実施しております。司法書士や税理士を中心とした相続・家族信託のプロフェッショナルチームが、「何をどうすればいいか分からない」といった段階から丁寧にサポートいたします。名古屋市で相続税対策をご検討中の方は、お一人で悩まずにぜひ当相談所にご相談ください。ご家族の状況に応じた最適なプランをご提案し、大切な資産の承継を安心・安全にお手伝いいたします。