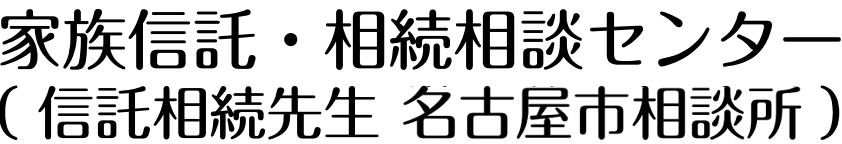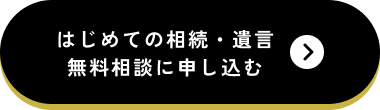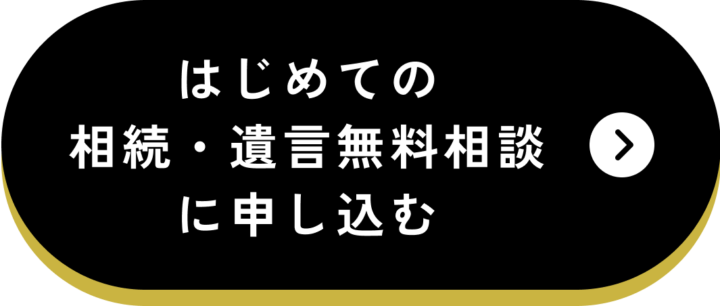相続税対策の基本:早めに知っておきたい生前対策のポイント
- 公開日:
- 更新日:
相続税対策は、高齢の親を持つ50代の子世代にとって、早めに取り組みたい重要なテーマです。相続税の制度は平成27年(2015年)の改正で基礎控除額が大幅に引き下げられ、これにより相続税の課税対象となるケースが増加しました。実際に相続税がかかった方の割合は亡くなられた方全体の約1割(令和5年時点で9.9%程度)に上ります。相続税の課税対象になる遺産規模に達すると、数百万円単位の税負担が生じるため、生前からの対策が欠かせません。そこで本記事では、相続税対策がなぜ必要かという理由から、知っておきたい相続税の基礎知識、生前にできる具体的な節税策の種類、そして対策の第一歩となる資産把握と専門家への相談について解説します。専門的な内容もできるだけ平易にまとめていますので、ぜひ今日からの相続税対策にお役立てください。
相続税対策が必要な理由(早めの準備の重要性)
相続税の課税対象が拡大
かつて相続税は一部の富裕層にだけ関係する税金という印象がありましたが、近年では一般の家庭にも無視できないものとなりつつあります。その背景には相続税の基礎控除額の引き下げがあります。2015年以降、相続税の非課税枠である基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に縮小され、例えば相続人が配偶者と子2人(法定相続人3人)なら4,800万円が基礎控除額となりました。このため、自宅不動産や預貯金など合計で4,800万円を超える遺産がある場合には相続税の申告・納税が必要になります。基礎控除額改正前は課税対象となるのは死亡者の数%程度でしたが、現在では約1割が相続税の課税対象となっています。都市部で自宅や土地を所有している家庭や、相続人が少なく基礎控除額が小さいケースでは、特別裕福でなくても相続税が発生し得る状況です。
生前対策は時間を味方に
相続税対策を早めに始める最大の理由は、時間をかけることで節税効果を高められる点です。例えば後述する暦年贈与(毎年110万円まで非課税の贈与)による資産移転は、年数をかけてコツコツ行うほど大きな節税効果が得られます。一方で、相続直前になって慌てて贈与しても、被相続人の死亡前3年以内の贈与財産は相続財産に加算され相続税の課税対象になってしまいます(※2024年からはこの持ち戻し期間が死亡前7年以内に延長)。早めに準備を始めれば、この「生前3年(→7年)ルール」の影響を避けつつ計画的に贈与を進めることが可能です。また、親御さんが元気なうちに対策を講じておけば、財産状況の把握や遺産分割の希望について家族で十分に話し合う時間も確保できます。早期からの生前対策は、相続税の節税だけでなく、将来の相続手続きや家族間のトラブル防止にもつながる点で重要と言えるでしょう。
相続税の基礎知識(基礎控除額・税率の仕組み)
相続税がかかる基準
相続税は、遺産総額(プラスの財産から借金や葬式費用を差し引いた正味の遺産額)が一定の非課税枠(基礎控除額)を超えた場合に、その超えた分に対して課税されます。基礎控除額は前述のとおり「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められます。例えば相続人が配偶者と子2人の場合、法定相続人は3人なので基礎控除額は4,800万円です。遺産総額がこの4,800万円以下であれば相続税は一切かかりません。逆に言えば、遺産が基礎控除額を1円でも超えると、その超えた部分に対して相続税の申告・納税義務が生じます。まずはご自身のご家庭の場合、基礎控除額がいくらになるかを把握しておくことが大切です。
税率と課税方法
相続税の税率は一律ではなく、課税対象となる遺産の額に応じた累進課税(段階的な超過累進税率)が適用されます。具体的には、基礎控除後の課税遺産総額をいったん法定相続人ごとに法定相続分で按分し、それぞれに10%から55%までの税率を適用して税額を算出します。その各人の税額を合計したものが相続税の総額となり、最後に実際の遺産分割に応じて各相続人の負担額を按分して決定します。簡略化すると「課税対象額が多いほど高税率が適用される」しくみで、例えば課税遺産総額が1億円を超える部分には30%、2億円超には40%、3億円超には45%…というように段階的に税率が上がり、最大で55%となります。こうした累進税率構造のため、遺産が大きい場合は相続税負担も高くなることを念頭に置く必要があります。
ただし、相続税には各種の控除・特例制度も用意されています。代表的なものが配偶者控除(配偶者に対する税額軽減)です。これは、配偶者が取得した財産については1億6,000万円までは相続税がかからない(または法定相続分相当額まですべて非課税)というものです。そのため、一次相続(最初の親の相続)では配偶者が全財産を相続すれば税額がゼロになるケースもあります。しかし、配偶者に財産を集中させすぎると、後の二次相続で子のみが多額の遺産を相続することになり、結果的に高い税率が適用されて相続税負担が増えてしまうケースが少なくありません。これについては後述する「二次相続まで見据えた対策」で触れます。
また、生命保険金については「法定相続人の数×500万円」の非課税枠があることも前述しました。例えば相続人が配偶者と子2人なら最大1,500万円までの死亡保険金が相続税の課税対象から除かれます(受取人が相続人以外の場合はこの枠は使えません)。この生命保険金非課税枠や、未成年者控除・障害者控除など他の税額控除を適用して最終的に相続税額がゼロになる場合でも、一度基礎控除額を超える遺産を取得していれば申告義務は生じます。以上を踏まえ、「基礎控除額」「累進税率」「各種特例」が相続税の基本的な仕組みと押さえておきましょう。
生前にできる主な相続税対策一覧
相続税を抑えるために、親が存命中に行える代表的な対策をいくつか紹介します。ご家庭の状況によって適する対策は異なりますが、以下の方法はよく活用されるものです。それぞれの仕組みとメリット・注意点を把握し、最適なプランを検討しましょう。
暦年贈与(毎年110万円まで非課税の贈与)
生前対策の基本とも言えるのが暦年贈与による資産移転です。毎年1月1日から12月31日までの1年間に個人が受け取った贈与額が110万円以下であれば贈与税がかからず、贈与税の申告も不要となります。この年間110万円の非課税枠をコツコツ使うことで、長期的に見て多額の財産を無税で移転できる可能性があります。例えば子ども1人に毎年110万円ずつ10年間贈与すれば合計1,100万円を無税で渡せます。相続人(受贈者)の数が多ければ各人に110万円ずつ贈与することで一度に数百万円規模の財産移転も可能です。また、暦年贈与は贈与する相手や使い道に制限がないため、教育資金や住宅資金など特定目的の資金援助だけでなく、どんな用途でも非課税枠を活用できる柔軟性があります。注意点として、毎年継続して贈与する場合は贈与契約書を作成しておき、贈与の事実関係を明確に残すこと、毎年同じ額・時期に贈与をしないよう変化をつけること(定期贈与と見なされない工夫)、親名義の預金を子名義に移すだけの名義預金に注意することなどが挙げられます。暦年贈与は早く始めるほど効果が高いため、余裕を持って計画的に行いましょう(2024年以降、相続開始前7年以内の贈与が段階的に相続財産に加算されることになりましたが、それでも長期にわたりコツコツ贈与した分は節税効果を発揮します)。
生命保険の非課税枠活用
生命保険を活用する相続税対策も一般的です。死亡保険金には法定相続人1人あたり500万円まで相続税が非課税になる特例があり、例えば相続人が配偶者と子2人なら合計1,500万円までの保険金が非課税扱いとなります。親御さんが生命保険に加入していれば、その保険金の一部が相続税の課税対象から外れるため、相続税負担を軽減できます。また、生命保険金は受取人固有の財産とされ、遺産分割協議の対象外です。あらかじめ指定された受取人が即座に保険金を受け取れるため、葬儀費用や納税資金に充当しやすいメリットもあります。さらに、保険契約の形を工夫し、子どもを契約者(保険料負担者)・親を被保険者・子どもを受取人とする形にすれば、保険金は相続税ではなく所得税(一時所得)の課税となり、50万円の特別控除や1/2課税の恩恵で結果的に税負担を下げられる場合もあります。ただしこの契約では子ども自身が保険料を払う必要があり、親御さんが高齢になると加入できないケースもあるため早めの検討が必要です。生命保険は非課税枠+迅速な資金確保というメリットがあり、相続税対策や納税資金準備として有効な手段です。
不動産への資産組み換えによる評価額引き下げ
現金・預金のまま財産を持っているより、不動産に形を変えることで相続税評価額を下げられるケースがあります。理由は、不動産の相続税評価額は市場価格よりも低く算定されることが多いためです。例えば現金1億円は評価額も1億円ですが、それを都市部の土地に替えると路線価評価では80%程度の8,000万円になるケースがあります。また、土地に賃貸アパートを建てて貸していると、土地は貸家建付地として約20%減額、建物も貸家として約30%減額され、実質評価額が半分以下になる可能性もあります。さらに、被相続人の自宅などに小規模宅地特例が適用できれば土地評価額が最大80%減額されます。こうした不動産活用により相続税の課税ベースを圧縮でき、結果として節税につながります。一方で、不動産は換金しづらく固定資産税や維持費もかかるため、流動性低下やコスト増といったデメリットもあります。賃貸経営がうまくいかず赤字になれば財産そのものが目減りしかねません。そのため、不動産による対策は節税効果とリスクを慎重に見極める必要があります。
二次相続まで見据えた対策
相続税対策は、最初の相続(一次相続)だけでなく配偶者が亡くなった後の二次相続まで踏まえて検討することが大切です。一次相続では配偶者控除で税額ゼロにできても、配偶者に財産を集中させすぎると二次相続で子だけが高額遺産を相続することになり、累進税率でトータルの税負担が増えることがあります。そこで、一次相続時に子にもある程度財産を相続させる工夫(例:配偶者50%・子50%で相続させる)をすると、二次相続時の相続財産総額を抑えられ結果的に税負担を軽減できます。また、夫婦それぞれが生命保険に加入しておけば、一次・二次それぞれで保険金非課税枠を使えるため、夫婦両方の死亡時に非課税枠をフル活用することも可能です。さらに、必要に応じて養子縁組で法定相続人を増やすことも基礎控除額を増やす策ですが(基礎控除額600万円×養子の数増)、家族関係に与える影響や上限人数(基礎控除で2人まで)に注意が必要です。
相続税対策の第一歩(資産把握と専門家への相談)
数ある対策の中から何を選ぶにせよ、まず取り組むべき第一歩は資産状況の把握と専門家への相談です。具体的には、現在親御さんがどれくらいの財産を持っているか一覧にまとめ、概算で相続税額をシミュレーションしてみましょう。金融資産は比較的把握しやすいですが、不動産の評価は路線価図や固定資産評価証明などが必要になります。可能であれば税理士に評価額を試算してもらうと正確です。現在の遺産総額が基礎控除額を超えそうかどうか、まずここで大枠を掴みます。それによって「暦年贈与を検討すべきか」「生命保険を活用すべきか」「現状のままで問題ないか」といった方向性が見えてくるでしょう。
資産把握ができたら、次に相続に強い専門家(税理士)に相談することをおすすめします。相続専門の税理士であれば、ご家庭の状況に応じて最適な相続税対策プランを提案してくれます。「このままだと相続税はいくらになり、どう対策すればどれだけ減るか」「一次相続・二次相続のトータルでどの分割プランが有利か」など、具体的な数字で比較検討できます。場合によっては、生命保険や不動産だけでなく、生前贈与(年間110万円の基礎控除枠の活用や住宅取得資金贈与の非課税特例など)を組み合わせた総合的な提案を受けられるでしょう。例えば、子や孫に対して住宅取得資金の生前贈与を行えば一定の非課税枠が使え、相続財産も減らせる、といった具体案です。
専門家に相談することで、最新の税制改正情報や見落としがちな節税手段も教えてもらえます。2024年以降の暦年贈与加算期間の延長や相続時精算課税制度の緩和など、法律は変化しますので、常に最新知識を持つプロの意見は非常に有益です。初回無料相談を実施している窓口も多いので、気軽に活用してみましょう。
名古屋市家族信託・相続の相談所など地域の相続専門相談センターでは、税理士・司法書士がチームで相談に応じてくれるところもあります。相続税対策はご家庭ごとに最適解が異なるものです。専門家の力も借りながら、「どの対策をいつ・どれくらい行うか」を計画的に検討していくことで、将来の相続に万全の備えができるでしょう。
相続、家族信託のご相談は名古屋市家族信託・相続の相談所へ
本記事では相続税対策の基本について解説しました。名古屋市家族信託・相続の相談所では、名古屋市にお住まいの皆様の相続税対策を経験豊富な税理士がサポートいたします。生前贈与や生命保険の活用、不動産の組み換えによる節税策など、お客様の状況に合わせたプランを初回無料相談にてご提案しております。相続税対策は早めの準備が肝心です。「何から始めればいいか分からない」「うちの場合どの対策が有効か知りたい」とお考えの方は、ぜひお気軽に当相談所までご相談ください。地域密着の専門家チームが、大切な資産を守るお手伝いをいたします。