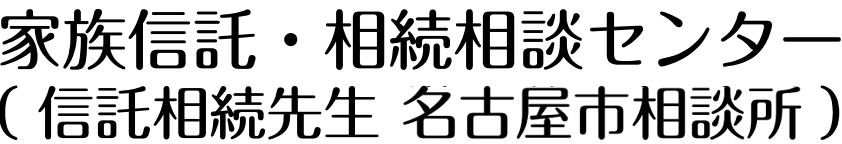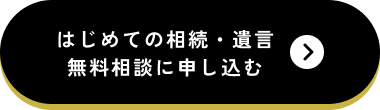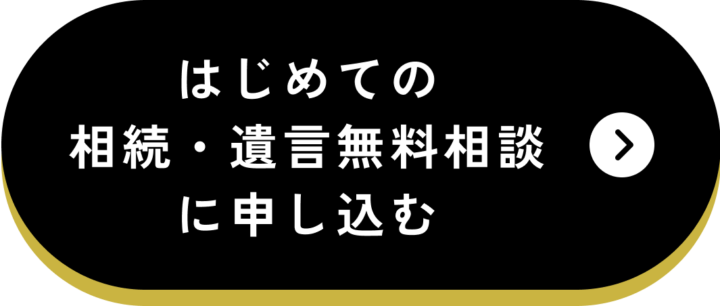家族信託はどんな場合に有効?活用事例と注意すべき点
- 公開日:
- 更新日:
家族信託はどのようなケースで特に効果を発揮するのでしょうか。万能ではないものの、状況によっては他の方法以上に有効な手段となります。本記事では、家族信託が有効に機能する主なケースをいくつかの活用事例として紹介し、併せて家族信託を利用する際の注意点について解説します。名古屋市で実際に寄せられる相談事例も踏まえ、高齢の親を持つ皆様に役立つ情報をお届けします。
家族信託が有効に機能する主なケース(活用事例)
まずは、家族信託の活用が効果的と考えられる代表的なケースを見ていきましょう。
認知症対策が必要なケース(判断能力低下に備える)
高齢の親が将来的に認知症になる可能性が高い場合、家族信託は最適な認知症対策となり得ます。例えば、名古屋市在住のXさん(75歳)は最近物忘れが増えており、自分の財産管理に不安を感じ始めました。Xさんと家族は、Xさん名義の自宅と預貯金を信託し、長女を受託者にすることで、万一Xさんの判断能力が低下しても娘が代わりに財産を管理できるよう備えました。このように、将来の判断能力低下による資産凍結リスクを回避できる点で、家族信託は大変有効です。
もし家族信託を利用せずXさんが認知症になってしまうと、銀行口座は凍結され、不動産の売却もできなくなります。その場合、成年後見制度を利用するしかなくなり、手続きの負担や制約が生じます。家族信託を導入しておけば、信頼できる家族が財産を管理し、介護費用の支払いなど柔軟に対応できるため、認知症対策として非常に心強い手段と言えるでしょう。
親の再婚や複雑な家族構成で遺産分割トラブルを防ぎたいケース
親が再婚している場合や、兄弟姉妹の間で血縁関係が複雑な場合(前妻・前夫との子がいる等)にも、家族信託は遺産分割のトラブル防止に効果を発揮します。例えば、父親Aさん(名古屋市在住)が再婚し、後妻Bさんと先妻との子どもCさんがいるケースを考えてみましょう。Aさんが何も対策せずに亡くなると、BさんとCさんの間で遺産分割協議が必要になり、利害の対立から揉める可能性があります。
そこでAさんは、生前に家族信託を活用し、自宅不動産を信託財産としました。受益者をAさん存命中はAさん自身、Aさん死亡後はBさん(後妻)とし、Bさんが亡くなった時点で最終的にその不動産をCさんに承継する——という内容の信託契約を結んだのです。こうしておけば、Aさん死亡後はBさんが引き続き自宅に住む権利を持ち、Bさん死亡後にCさんが確実に不動産を取得できます。このスキームにより、後妻と先妻の子の間の遺産争いを未然に防ぐことができました。
このように、家族構成が複雑で相続トラブルが心配な場合、家族信託によって各人の取り分や権利を事前に定めておくことで、争いの火種を小さくできます。遺言でもある程度の指定は可能ですが、信託なら生前から資産管理を調整でき、二次相続に至るまで一貫した承継プランを組める点がメリットです。
障がいのある子への財産承継や二次相続まで考慮したいケース
ご家族に障がいをお持ちの子どもがいる場合や、配偶者亡き後の財産承継(二次相続)まで見据えたい場合も、家族信託は有力な手段です。例えば、名古屋市のYさん夫婦には知的障がいを持つ長男がいます。自分たちに万が一のことがあったとき、長男が適切に財産管理できるか心配でした。そこでYさん夫婦は、自宅と金融資産を信託に組み入れ、次男を受託者兼長男の後見人的な立場とする契約を結びました。内容は、夫婦が健在な間は夫婦が受益者として財産を利用し、夫婦亡き後は長男を受益者として次男が長男の生活費等に信託財産を充てる、そして最終的に長男が亡くなった時点で残余の財産を次男が受け継ぐ——というものです。
この信託によって、夫婦死亡後も障がいのある長男の生活が経済的に保障され、長男自身が財産管理できなくても次男が責任をもってサポートできます。また、長男死亡後の財産の行き先まで定めてあるため、次男は安心して管理に従事できます。家族信託がなければ、長男名義で相続した財産を次男が管理するには成年後見人になる必要がある上、長男死亡時には改めて相続が発生してしまいます。このケースでは、信託によって二次相続の発生を事実上スキップし、財産承継をシンプルかつ確実にできた点が大きな利点です。
障がい者の生活保障や二次相続対策として、家族信託は非常に有効です。なお、特定の障がい者を受益者とする信託には税法上の特例(贈与税・相続税の非課税枠拡大)もあります。家族状況に応じて、こうした制度も活用しながら信託設計をすると良いでしょう。
親の保有する収益不動産の管理・承継を円滑に行いたいケース
親が賃貸マンションや貸駐車場など収益不動産を所有している場合、その管理・承継のために家族信託を使う方法があります。例えば、名古屋市内で複数の賃貸物件を経営している高齢の父親Dさんがいるとします。Dさんは年齢的に物件管理が負担になってきたため、長女に管理を引き継ぎたいと考えました。同時に、自身に何かあった際には不動産収入を配偶者や子どもたちに確実に渡るようにしたいとも望んでいます。
そこでDさんは、所有する賃貸マンション群を家族信託に組み入れ、長女を受託者に任命しました。Dさんが健在のうちは受益者をDさん本人とし、毎月の賃料収入はDさんの生活費等に充てます。管理業務は長女が担うため、Dさんは日常の煩雑な業務から解放されます。そしてDさんが亡くなった後は、長女が引き続き物件を管理しつつ、その収益を母親(Dさんの妻)および兄弟に分配するという形で信託を運用する計画です。
このように家族信託を使えば、親から子への賃貸事業承継的な資産引き継ぎがスムーズに行えます。親の存命中から子が管理を担うことでノウハウ継承もでき、親に万一のことがあっても収入の流れが途切れません。信託登記を済ませておけば、金融機関との取引や第三者への賃貸借契約も受託者名義で問題なく継続できます。不動産オーナーの高齢化に伴い、名古屋市内でもこのような形で早めに資産管理を子世代に移行させる家族信託の活用事例が増えています。
家族信託を利用する際の注意点
以上のようなケースで家族信託は大いに役立ちますが、実際に利用する際にはいくつか注意すべき点があります。ここでは代表的な注意事項を確認しておきましょう。
他の相続人への説明・同意など事前調整の必要性
家族信託は法律上は委託者(親)と受託者(子など)の契約で成立しますが、他の相続人となる家族の理解と協力を得ておくことが極めて重要です。信託契約そのものに兄弟姉妹の同意は不要とはいえ、事前に説明なく特定の子だけが財産管理を任されたりすると、後から「自分たちは蚊帳の外だった」と不満を抱かれる恐れがあります。
円満に家族信託を運用するには、他の家族への丁寧な説明と事前調整が欠かせません。例えば、受託者になる子どもの兄弟に対しては、信託の目的や内容をきちんと伝え、合意を得る努力をしましょう。必要であれば、信託契約書の写しを共有したり、専門家から第三者的に説明してもらったりするのも有効です。名古屋市のあるご家庭でも、長男を受託者とする信託を結ぶ際、次男・三男に事前に相談し理解を得ていたことで、後々まで円満に資産管理ができた例があります。
逆に説明不足のまま信託を進めてしまうと、後から他の相続人が「そんな話は聞いていない」と納得せず、信託の無効を主張して揉めるケースもあります。家族信託は家族の協力あってこそ円滑に機能するものです。契約前に十分な話し合いを行い、可能であれば書面に残すなどして、全員が納得の上でスタートするようにしましょう。
信託財産の範囲・内容に関する制限(預貯金や年金は信託不可 等)
家族信託で管理できる財産には、一部制限もあります。基本的に現金、不動産、有価証券などの資産は信託財産とできますが、年金受給権のように個人に属する権利は信託にできません。公的年金は受給者本人の口座にしか振り込まれないため、信託契約の対象から外す必要があります(受領後の年金額を信託口口座に移すことは可能です)。
また、預貯金債権そのものは信託可能ですが、銀行口座名義を直接信託に切り替えることはできません。一度引き出して信託口口座に預け入れる形で管理します。その他、農地は農地法の制約があり信託できないケースがありますし、契約者本人以外に権利移転ができない生命保険の保険契約なども信託の対象外です。信託で扱えるか微妙な資産については事前に専門家に確認し、必要に応じて別の制度(例えば生命保険金は受取人指定の工夫、農地は市街化など転用の検討 等)を検討することが大切です。
信託の運用管理中に起こり得るトラブル(受託者の不正など)
家族信託は開始して終わりではなく、その運用期間中にも注意すべき点があります。まず、受託者の不正リスクです。極めて稀なケースではありますが、受託者が信託財産を私的に流用したり、管理を怠ったりするトラブルが起こり得ます。家族とはいえ金銭が絡むと人が変わってしまう可能性がゼロとは言えません。対策としては、信託監督人や受益者代理人を契約で定めておき、受託者の行為をチェックできる仕組みを入れることが有効です。また、定期的な報告を義務付け、他の家族も通帳残高や収支を確認できる環境を整えると不正の抑止になります。
次に、受託者の交代や死亡に関するトラブルです。長期にわたる信託では、受託者自身が高齢になったり病気で職務続行が難しくなることもあります。契約時に後任の受託者を指定していなかった場合、受託者不在の事態となり信託が機能不全に陥りかねません。こうした事態を避けるため、契約書に「受託者が辞任・死亡した場合は◯◯が後任受託者となる」といった条項を盛り込んでおくことが望ましいでしょう。
税務上の取扱い(信託による税負担の変化に留意)
家族信託を利用しても、税金の負担が劇的に減るわけではありません。信託はあくまで財産管理・承継の手法であり、税務上は従来と同様の課税が行われると考えておく必要があります。例えば、親が自分を受益者として財産を信託した場合、生前は従来通り親に所得税や固定資産税等が課されますし、親が亡くなって子どもが財産を引き継げば相続税の課税対象になります(信託だからといって相続税が免除されることはありません)。
むしろ注意すべきは、信託の形によっては贈与税等の課税タイミングが生じる可能性がある点です。例えば、親が受益者ではなく子どもを受益者とする形で財産を信託すると、それは親から子への贈与とみなされ贈与税課税の対象となります。また、2024年の税制改正によって相続開始前7年以内の生前贈与は相続税に加算される期間が延長されましたが、信託による財産移転もその例外ではありません。相続直前に信託で名義を移し換えても節税にはならず、計画的な対策が必要です。
以上より、家族信託を検討する際は税理士などにも相談し、税務面で不利にならない形で設計することが重要です。特に複数世代にまたがる信託の場合、各タイミング(信託設定時、受益者変更時、信託終了時)でどのような税がかかるか把握しておきましょう。
家族信託のご相談は名古屋市家族信託・相続の相談所へ
家族信託が効果的なケースとして、認知症対策、複雑な家族関係の相続対策、障がい者支援、収益不動産の承継などを見てきました。これらの事例から分かるように、家族信託は**「こんな場合に有効」というはっきりした得意分野**を持つ制度です。一方で、利用にあたっては事前の家族間調整や信託財産の範囲に関する制約、運用中の管理留意点、税務面の確認など、注意すべきポイントも少なくありません。
大切なのは、これらメリットとリスクを踏まえて適切に設計・運用することです。今回挙げた活用事例に自分の家庭状況が当てはまる方は、家族信託の活用を前向きに検討すると良いでしょう。その際には専門家の助言を受けながら、注意点もしっかりクリアする形で進めることをおすすめします。
名古屋市でも家族信託の相談件数は増えており、専門家チームによるサポート体制が整っています。安心して制度を活用するためにも、まずは気軽に相談から始めてみてはいかがでしょうか。
家族信託のご相談は名古屋市家族信託・相続の相談所へお気軽にお問い合わせください。