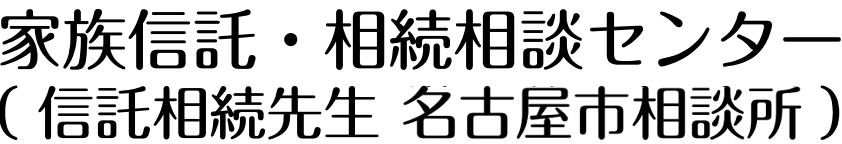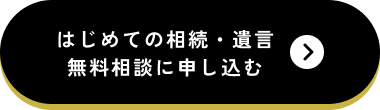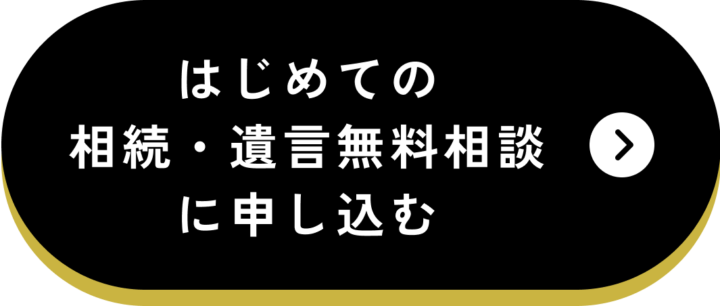家族信託の始め方と手続きの流れ:準備から契約まで徹底解説
- 公開日:
- 更新日:
「家族信託を始めたいけれど、具体的に何から手を付ければいいのか分からない」という声をよく耳にします。初めて家族信託を利用する方にとって、準備や手続きの流れが見えないと不安になりますよね。本記事では、家族信託の始め方として準備段階から信託契約の締結までの一連の流れを、名古屋市のケースも交えながら徹底解説します。必要な書類や費用の目安、専門家への相談ポイントも紹介しますので、初心者の方でも手順がイメージできるでしょう。
家族信託を始める前に準備すべきこと
スムーズに家族信託を進めるには、契約を結ぶ前の準備が肝心です。以下のステップを踏んで、事前準備を整えましょう。
資産・財産の洗い出しと信託計画の明確化
まずは、親御さんがお持ちの資産をすべて洗い出すことから始めます。不動産(土地・建物)、預貯金、株式や投資信託、車や貴金属といった貴重品まで、信託に組み入れたい財産を一覧にまとめましょう。また負債(住宅ローンなど)があればそれも確認しておきます。
次に、それらの財産を今後どのように管理・承継したいかという信託計画を明確にします。誰を受益者とし、財産から生じる利益をどう使うのか、最終的に財産を誰に引き継ぐのか(残余財産の帰属先)など、信託の目的と大枠の設計を考えます。例えば「父の自宅と預金を信託し、父が亡くなるまでは父自身を受益者として生活費や介護費用に充てる。父の死後はその財産を子ども二人に●●割合で分配する」というように、具体的なイメージを固めておくと良いでしょう。
名古屋市の不動産をお持ちの場合は、その評価額やローン残高なども事前に確認しておくことをおすすめします。信託すべき財産の範囲を決め、信託契約で定める内容(条項)の骨子が見えてきたら、次のステップに進みましょう。
家族間での話し合いと受託者(託す相手)の選定
信託計画の方向性が決まったら、家族内で十分に話し合いを行うことが重要です。親(委託者)だけでなく、将来財産を受け取る予定の子どもたち(受益者予定者)も含め、家族全員で信託の目的と内容を共有しましょう。「なぜ家族信託を行うのか」「信託財産や受益者は誰にするのか」といった点に家族の合意が得られていることが理想です。この段階でしっかりコミュニケーションを図っておくことで、後々のトラブル防止につながります。
特に受託者(財産を託され管理する人)の選定は慎重に行いましょう。一般的には信頼できる長子や近親者が選ばれますが、その人が管理責任を担えるか、他の家族も納得できるかを考慮します。例えば、長男を受託者にする場合でも、次男・三男にも「長男に任せる」ことを理解してもらうことが大切です。必要に応じて、信託監督人や第二受託者(予備の受託者)の指定についても家族で話し合っておくと安心です。
専門家(司法書士・弁護士)への相談
信託計画の概要と家族の合意形成ができたら、早めに専門家に相談することをおすすめします。家族信託の実務に詳しい司法書士や弁護士であれば、計画の妥当性をチェックし、法律的に不備のない契約内容となるよう助言してくれます。また、税理士に相談して信託に伴う税金の確認をしておくことも有益です(信託そのものに節税効果はありませんが、贈与税・相続税の扱いなど念のため確認すると良いでしょう)。
専門家に依頼すれば、名古屋市内の公証役場での契約手続きや法務局での登記申請などの実務も代行してもらえるため、手続き全体がスムーズに進みます。初回相談は無料で対応している事務所も多いので、「何から始めればいいか分からない」という段階でも気軽に問い合わせてみましょう。当センター(名古屋市家族信託・相続センター)でも、家族信託に精通した司法書士がご相談を承っています。
家族信託契約の手続きと流れ
では、実際に家族信託契約を結ぶ際の具体的な手続きと流れを見ていきます。
信託契約書の作成(条項の決定と公正証書化)
専門家のサポートを受けつつ、信託契約書の詳細を詰めていきます。信託財産の範囲、受託者の権限や義務、受益者や残余財産の受取人の指定、信託の終了事由など、信託契約の条項を一つひとつ検討します。家族信託はオーダーメイドの契約ですから、ご家庭の事情に合わせて条項を設定できます。不動産を売却する際の条件や、受託者が辞任・死亡した場合の対応策など、将来起こり得る事態も視野に入れて取り決めておくと安心です。
契約内容が固まったら、信託契約書を作成します。公正証書にする場合は、公証役場で公証人に作成してもらいます。公証役場では公証人が契約内容を法律的にチェックし、当事者全員が署名・押印することで正式な契約書となります。公正証書にしておけば原本が公証役場に保管されるため紛失の心配もなく、内容の信頼性も高まります(私人間の私署契約より証明力が強く、安全です)。名古屋市内にも複数の公証役場がありますので、日程を予約して関係者(委託者・受託者)が出向き、契約締結を行います。
信託口口座の開設・信託財産の名義変更(登記など)
信託契約を締結したら、次に信託の実行に伴う各種手続きを行います。まず、預貯金などの金銭を信託した場合には、信託専用の銀行口座(信託口口座)を開設し、信託財産として預金を管理します。多くの金融機関で家族信託用の口座開設に対応しており、委託者と受託者が契約書を持って窓口で手続きを行います。信託口座に資金を移し替えることで、信託財産と受託者個人の財産が明確に分離されます。
次に、不動産を信託した場合は**不動産の名義変更(信託登記)**を行います。土地や建物の登記簿上の所有者を受託者名義に変更し、「信託」を原因とする旨の付記を加える登記手続きです。これにより、第三者から見てもその不動産が信託財産であることが明らかになります。信託登記は司法書士に依頼して法務局で申請してもらうのが一般的です。
その他、株式や投資信託を信託する場合は証券会社での名義書換え、借入金がある場合は金融機関への通知など、個別の資産に応じた手続きを進めます。これらの移管手続きが完了すれば、家族信託の運用が正式にスタートします。
信託開始後の管理・定期報告の方法
家族信託がスタートした後も、適切な管理とフォローが大切です。受託者は信託財産を管理・運用しつつ、その状況を受益者(親)に報告していきます。委託者=受益者である親が健在なうちは、受託者が随時状況を伝えていれば特に定期報告の義務はありません。しかし、親が判断能力を失っている場合や、受益者が親以外に移った場合には、定期的に財産の収支や残高をまとめた信託財産状況報告書を作成し、家族や関係者に共有すると良いでしょう。
また、信託期間中に状況の変化があれば契約内容の見直しを検討します。例えば、受託者を交代する必要が生じた場合や、信託財産を追加したい場合など、契約の変更や追加を行う際は専門家に相談しながら適切な手続きを踏みます(公正証書の変更手続きや登記の変更が必要になることがあります)。
重要なのは、信託を家族の中で「見える化」しておくことです。受託者だけが内容を把握している状態では他の家族が不安になりかねません。定期的な情報共有や話し合いの場を設け、信託が当初の目的どおりに機能しているかを皆で確認すると安心です。こうした透明性の確保が、長期間にわたる家族信託を円滑に運用するポイントとなります。
家族信託にかかる費用と必要書類
次に、家族信託を始める際に必要となる費用の目安と、準備しておくべき書類について説明します。
契約書作成費用・登録免許税など費用の目安
家族信託に関わる主な費用は、契約関連費用と手続き関連費用に大別できます。
- 契約関連費用: 信託契約書の作成にかかる費用です。専門家に依頼する場合の報酬(内容の複雑さによりますが数十万円程度が目安)、公正証書にする場合の公証人手数料(例えば財産額5000万円程度の信託契約なら5~6万円前後)などが発生します。また、公正証書作成時の印紙代・謄本交付料も数千円ほどかかります。
- 手続き関連費用: 不動産の信託登記にかかる登録免許税(評価額の0.4%)や登記を依頼する司法書士の報酬、信託口口座を開設する際の銀行手数料(銀行によっては数千円程度かかる場合があります)などが該当します。例えば評価額1億円の不動産を信託すれば登録免許税だけで40万円となり、決して小さくない負担です。
この他、信託を開始した後も、財産の管理に関連して専門家にサポートを依頼すれば別途費用が発生する場合があります(例えば、税申告や不動産管理を専門家に委託する場合など)。いずれにせよ、家族信託には一定の初期費用がかかる点を踏まえ、計画段階で資金準備しておくことが大切です。
準備しておくべき書類(財産目録、登記関連書類 等)
家族信託の手続きに必要となる主な書類は以下のとおりです。
- 財産目録: 信託に組み入れる資産の一覧表です。不動産の所在地・評価額、預貯金の残高、証券口座の内容などをまとめます。
- 本人確認書類・印鑑証明書: 委託者(親)・受託者(子)それぞれについて運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書、および実印の印鑑証明書(発行後3か月以内)が必要です。
- 不動産関係書類: 不動産を信託する場合、登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産評価証明書が必要です。登記事項証明書は法務局で、評価証明書は名古屋市役所(資産税課)や各区役所で取得できます。
- 金融資産関係書類: 預貯金なら通帳や残高証明書、株式・投資信託なら証券会社の残高報告書等、金融資産の現状がわかる資料を用意します。
- その他の資料: 家族構成が分かる戸籍謄本(受益者や相続人関係を確認するため)、信託契約の草案(専門家と相談している場合)などがあると手続きが円滑になります。
実際には専門家に相談すれば、ケースに応じた必要書類リストを提示してもらえます。早めに必要書類を収集しておくことで、公証役場での契約や登記申請もスムーズに進むでしょう。
家族信託のご相談は名古屋市家族信託・相続の相談所へ
家族信託の始め方と手続きの流れを順を追って見てきました。大切なのは、事前準備と専門家のサポートです。財産の洗い出しから家族の合意形成までしっかり行い、その上で信頼できる専門家の力を借りれば、初めてでも安心して家族信託を開始できます。名古屋市で家族信託を検討されている方も、地域の実情に詳しい司法書士等と連携することで、煩雑な手続きを円滑に進められるでしょう。
ご家族の大切な財産を守り、将来に備える家族信託。今回解説したポイントを参考に、ぜひ早めの準備と行動を心がけてください。
家族信託のご相談は名古屋市家族信託・相続の相談所へお気軽にお問い合わせください。