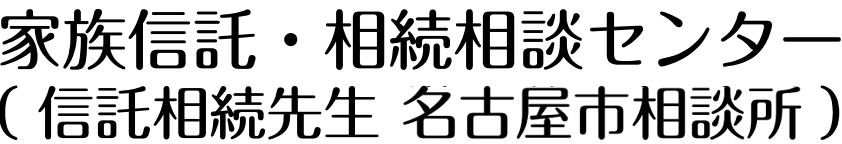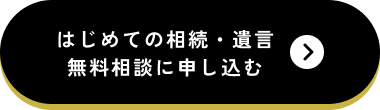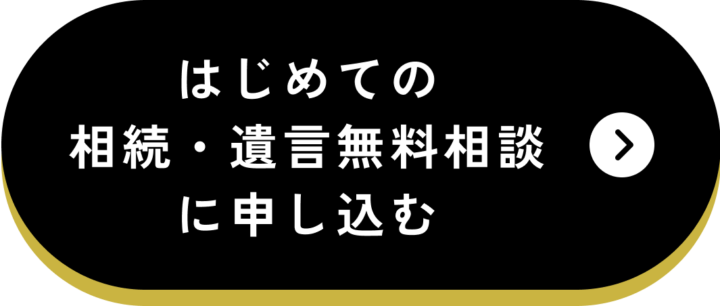未登記借地権と家族信託の注意点
- 公開日:
- 更新日:
はじめに
未登記の借地権を家族信託に組み入れるケースでは、法律上の論点と実務上の注意点を正確に把握しておく必要があります。家族信託(民事信託)は高齢者の財産管理や相続対策として普及が進んでおり、不動産を信託財産にする事例も増えました。中でも、借地上の建物を信託する場合は、その土地賃借権(借地権)も信託財産に含めなければなりません。しかし借地権が未登記だと、第三者対抗要件や信託登記に絡む特殊な問題が生じます。さらに、地主の承諾という大前提もクリアしなければなりません。
本稿では、未登記借地権を信託財産とする家族信託の要点を解説します。借地借家法10条や民法612条、信託法14条・34条などの関連法規を踏まえ、信頼性の高いスキームを構築するための実務ポイントとリスク対応策を示します。論点ごとに平易に説明しつつ、現場で留意すべき注意点や専門家ならではのアドバイスを織り交ぜます。
未登記借地権の信託における主要論点
未登記借地権を信託する際に特に重要となる論点は、次の3つに大別されます。
- 借地権の第三者対抗要件の維持
(借地借家法10条と建物登記に関する問題) - 信託財産の対抗要件と分別管理
(信託法14条・34条の適用および非登記資産の扱い) - 借地権譲渡に伴う地主承諾と実務対応
(民法612条の承諾要件、承諾書の内容、承諾料や裁判所許可制度など)
以下、それぞれについて詳しく解説します。
借地借家法10条による対抗要件と信託への応用
借地権(土地賃借権)の第三者対抗要件については、借地借家法10条が特別ルールを定めています。同条第1項により、借地権そのものの登記がなくても、借地上に借地権者名義で登記された建物を所有していれば、その借地権を第三者に対抗できるとされています。平たく言えば、「建物の登記」で借地権の存在を公示する制度です。実務上、借地権者(借地人)は土地賃借権の登記をすることは稀ですが、その代わりに借地上の建物を自己名義で登記して対抗力を確保するのが一般的です。
家族信託の文脈では、委託者(元の借地人)から受託者(新たな借地人)へ借地権が移ります。このとき肝心なのは、借地借家法10条の要件を満たし続けることです。すなわち、受託者名義で建物が登記されている状態を維持する必要があります。信託契約によって建物所有権が受託者に移転したら、速やかに受託者への所有権移転登記と信託の登記(信託目録の記載)を行います。これで受託者(現借地権者)が登記された建物を所有していることになり、借地権の第三者対抗力が保たれます。
注意すべきは、建物が滅失・取り壊しになる場合です。借地借家法10条は建物の存在が前提なので、建物が無くなると原則として借地権の対抗力も失われます。10条2項で一時的に対抗力を維持する措置(滅失後2年間の掲示による保護)が認められていますが、いずれにせよ信託中に建物を再築する際などは地主承諾も含め慎重な手続が必要です。建物の名義と存続こそが借地権の権利主張の基盤である点を、常に念頭に置いておきましょう。
信託法14条・34条と未登記借地権:対抗要件と分別管理
信託法14条は、信託財産に属することの対抗要件を定めた条文です。本来登記や登録を要する財産については、信託による権利移転でも信託登記等をしなければ第三者に対抗できないと規定しています。例えば不動産であれば所有権移転と同時に信託登記をしないと、受託者が「それは信託財産だ」と第三者に言えないということです。これは先述の借地借家法10条とも通じる概念ですが、より一般化した信託特有の規定と言えます。
では、未登記の土地賃借権(借地権)はこの「登記を要する財産」に当たるでしょうか。ここが理論上の争点です。土地賃借権自体は民法177条の「不動産に関する物権変動」ではなく債権ですが、借地借家法10条という特則で事実上登記に準じた対抗制度が設けられています。したがって学説上は、信託法14条を厳密に適用して信託登記ができない以上第三者に対抗不可とみる肯定説と、そもそも借地権は建物登記で対抗力を得ているので信託登記は不要とみる否定説が対立しています。
実務的には判然としない部分ですが、少なくとも受託者の義務としては信託法34条の分別管理義務が強く関係してきます。信託法34条は、受託者に対し信託財産と自分の財産等を明確に区別して管理することを義務付けています。登記・登録ができる財産は信託登記等をすることが分別管理の方法とされています(34条1項各号)し、登記できない財産についても帳簿管理や物理的分離によって区別し管理しなければなりません。
未登記借地権はまさに「登記(信託)できない財産」に該当します。この場合、受託者は他の財産と混同しないよう管理する責務があります。例えば、借地権に関する契約書や信託契約書、帳簿類においてその権利が信託財産であることを明示する、借地から生じる収入(地代収入や転貸賃料など)があれば信託専用口座で管理する、などの措置が考えられます。こうした分別管理の工夫は、信託法14条の「公示」に直接は当たらないとしても、第三者に対する事実上の対抗力の裏付けとして機能します。受託者の一般債権者が信託財産を差し押さえようとした際も、信託専用口座や明確な帳簿があれば「この財産は信託財産だ」という主張に説得力を持たせられます。
結論として、信託法14条の問題はグレーゾーンであるものの、実務では信託法34条の遵守を徹底し、できる限りの分別管理策を講じることが重要です。それによって「信託財産であることを第三者にもわかる状態」に近づけ、万一の紛争時に備えることができます。
地主承諾と承諾書作成、承諾料・裁判所許可の扱い
地主の承諾取得は、借地権信託における実務上最大のハードルかもしれません。民法612条により賃借権の譲渡には地主の承諾が必要とされ、信託も形式上は譲渡に当たるため例外ではありません。まずは地主に信託の趣旨を丁寧に説明し、理解と協力を得ることが欠かせません。
承諾を得る際には、単なる口頭同意ではなく書面(承諾書)を作成します。承諾書には「借地権およびその目的である借地上建物を信託契約に基づき受託者に移転すること(借地権譲渡)を承諾する」旨を明記します。その際、信託期間中に受託者が交替した場合や信託終了時に借地権が委託者や他の者に移転する場合も包括承諾を得ておくと、後々の手間が省けます。また、信託後も土地賃貸借契約の条件(地代や契約期間等)は従前通り維持されること、委託者(元借地人)が受益者として引き続き建物を使用する場合は無断転貸ではなく地主も容認すること、などの条項を盛り込んでおくと安全です。
承諾料(名義書換料)については、地域や条件によりますが借地権価格の10%程度が相場とされます。家族内で名義を変えるだけとはいえ、法律上は譲渡なので地主が承諾料を請求するのは一般的です。しかし、交渉次第で減額や免除の余地もあります。たとえば、「今回は財産管理の都合で名義を変えるだけであり、利用状況も地代も今まで通り」という点を強調し、地主に実害がないことを理解してもらえれば、「それなら承諾料は要らないですよ」となるケースもあります。実際、信託設定時の受益者が元の借地人本人で居住継続する場合などは、地主も安心感を持ちやすく、承諾料の減額交渉が成立しやすい傾向です。
もし地主が承諾しない場合の対応策が借地借家法19条の裁判所許可(借地非訟)です。これは最終手段ですが、「承諾料を供託するから許可してほしい」「借地人側に特段瑕疵はない」といった事情を立証できれば、裁判所が地主に代わって譲渡許可を出してくれることがあります。許可が降りれば法的には承諾があったのと同じ効力になります。ただし、裁判所は地主の利益も勘案して、条件として借地条件の変更(地代の増額等)を求めたり、承諾料の額を調整したりすることがあります。時間と費用もかかるため、現場ではできる限り裁判所手続に頼らず、地主と直接交渉して合意形成することが望ましいでしょう。
まとめると、地主承諾の段階では、次の要素を検討します。専門家としては地主の不安を解消する説明スキルと、承諾書ひな型の準備が求められます。
- 事前説明と交渉
- 承諾書への的確な記載
- 承諾料の調整
- 裁判所許可のオプション
実務対応策の詳細:安全に借地権を信託財産とするために
上記主要論点を踏まえ、未登記借地権付き不動産を家族信託する際の具体的な対応策を以下に整理します。
建物の名義変更と信託登記の確実な実施
- 所有権移転及び信託登記: 信託契約が発効したら速やかに借地上建物の所有権移転(委託者→受託者)及び信託登記を行います。信託登記では、信託目録に借地権も信託財産だと明記しておくことで、利害関係人への公示効果を高めます。
信託契約書・公正証書の活用
- 公正証書化: 信託契約書は公正証書にします。契約日や内容が公的に証明され、万一の訴訟時に強力な証拠となります。特に未登記の権利を扱うときは確定日付のある公正証書が安心です。
分別管理と信託専用口座
- 専用口座の開設: 受託者名義で新たに預金口座を開設し、信託財産専用口座とします。金融機関側においても分離取扱いされる口座が理想ですが、難しい場合は信託契約書内で信託財産を管理する口座を特定します。
- 金銭の流れの区別: 借地上建物からの賃料(例えばアパート収入)があるなら必ず信託口座で受領し、地主への地代支払いも信託口座から行います。他の個人的な入出金と混同させません。帳簿上も信託財産の収支科目を独立させて管理し、受益者へ定期報告します。
地主承諾と承諾書の適正な取り交わし
- 早期交渉: 信託の構想段階で地主に相談し、信託の目的(高齢の親の財産管理等)や受託者の人物像(親族であること等)を伝えます。地主に不信感を与えないことが肝要です。必要に応じて、信託の制度資料や、信託契約の概要などを提示することで円滑に進められるでしょう。
- 承諾書作成: 専門家として承諾書のひな型を用意し、地主に署名押印をお願いする形を取ります。ポイントは前述のとおり、譲渡内容の特定、包括承諾、契約条件不変更、受益者使用承諾、建替え・担保設定の扱い、承諾範囲の限定など盛り込むことです。承諾日と物件表示、当事者表示も正確に入れます。
- 承諾料の授受: 承諾料を支払う場合は金額と支払日を明記し、領収書ももらいます。減額や免除となった場合も、その旨を承諾書に「承諾料は徴収しない」等書いてもらうと安心です。
- 承諾書の保管: 原本は重要書類として受託者または関与専門家が保管します。信託期間中に地主が変わったら、新地主にコピーを提示して承諾の事実を引き継ぐようにします。
その他(信託期間中・終了時の対応)
- 信託期間中: 建物の老朽化による建替えや、大規模修繕で融資を受ける場合など、都度地主に相談・承諾を得るようにします。承諾書で包括承諾が取れていても、事前に知らせておくことでトラブルを避けられます。
- 受託者交替時: 受託者が死亡等で交替する際、新旧受託者と地主との間で改めて確認書を交わすと親切です(包括承諾があれば法的には不要ですが信頼維持のため)。
- 信託終了時: 借地権と建物を帰属権利者(通常は受益者またはその相続人)に名義戻しする登記が必要です。これも法律上は譲渡なので、承諾書に名義戻しを含めていなかった場合は地主承諾または裁判所許可が必要になります。初めから包括承諾を得ておくのが理想ですが、漏れた場合は終了前に地主と交渉します。
以上が主な実務対応策です。次に、これらの対応策を実践する上での留意点を述べます。
専門家から見た注意点
法律関係の整理と説明責任
家族信託に未登記借地権を組み込むには、借地借家法・民法・信託法の交錯する問題を整理する必要があります。専門家はまず自ら法的整理を行い、それを依頼者や地主にもわかりやすく説明する役割を負います。専門家の丁寧な説明が円滑な承諾取得と信託実現のカギとなります。
想定外の事態への備え
信託期間中に想定外の事態が起こることもあります。例えば、受託者が急逝したような場合。こうした場合にも備えて、信託契約書に予備的な条項(後継受託者の指定)を入れておくと安心です。また地主交代時は、新地主に信託の経緯を説明し、必要なら再度承諾を得るなど柔軟に対応します。
他専門家との連携
借地権の評価や承諾料の妥当性判断には、不動産鑑定士の助言を仰ぐ場合もあります。また、信託スキーム全体の税務面(登録免許税や不動産取得税、信託解除時の贈与税リスクなど)について税理士と協議することも重要です。家族信託は多角的な分野にまたがるため、必要に応じて各分野の専門家と連携し、依頼者に最適な提案を行います。
ケースによる柔軟な判断
最後に、すべてのケースで家族信託がベストとは限らないことも指摘しておきます。例えば地主との関係が極めて悪く承諾が得られそうにないとか、承諾料が非常に高額で費用対効果が見合わない場合もあるでしょう。その場合、任意後見契約で対応するとか、遺言で名義を戻す形で相続させる等の代替策も検討します。
おわりに
未登記借地権を信託財産とする家族信託について、法律面の論点と実務対応策を総合的に解説しました。要点を振り返ると、借地借家法10条の対抗力維持、信託法14条・34条への対応(分別管理の徹底)、地主承諾と承諾書整備の3本柱が重要でした。専門家の役割は、依頼者家族と地主双方の立場を理解しつつ、法律に則った適切な助言と手続きを行うことです。
借地権は複雑で慎重な扱いが必要ですが、本稿で取り上げた知識と対策を踏まえていただければ、未登記借地権を含む家族信託案件にも十分対応できるでしょう。適切なスキーム設計と丁寧な関係者調整により、依頼者にとっても地主にとっても安心できる信託を実現していただきたいと思います。